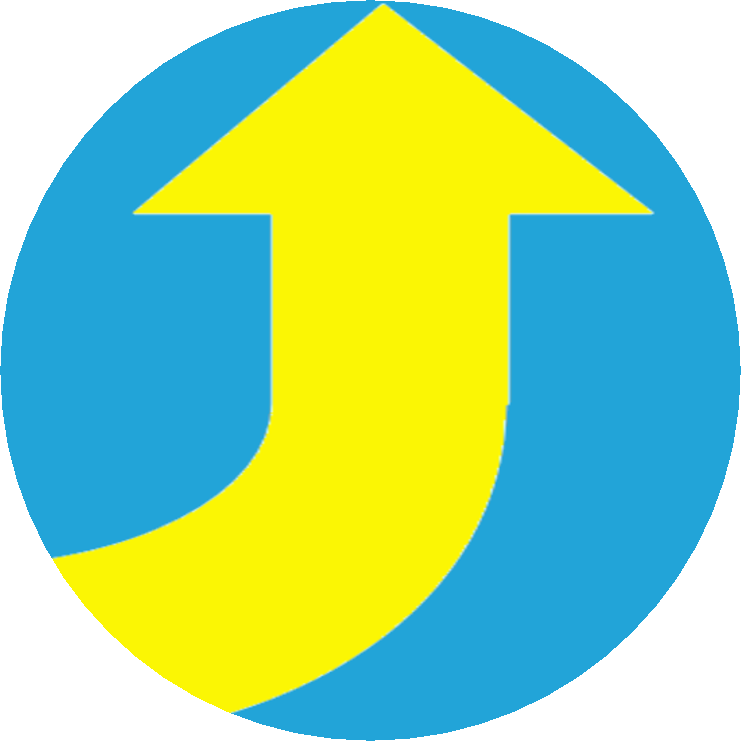はじめに
高校の進路指導は、年々早まっています
高1・高2の段階で「指定校推薦での大学進学」を強く意識させられる生徒も少なくありません
一方で、今、問題になっているのが「指定校推薦で入学したものの、大学を辞めてしまう学生の急増」です
進路選びでは、親の意向が強く反映されることも多く、子どもが言い出せないまま進学してしまうこともあります
本当にその進路は「子どもにとって無理はないか、大丈夫か?」
親子で、今のうちに確認しておきたい「指定校推薦の注意点」をお伝えします
第1章 指定校推薦=「安全」ではない時代に
指定校推薦と聞くと、
「一度決まれば確実に進学できる」
「受験しなくて済む」
といった安心感が先行します
ですが、現実には、
「入ってから後悔した」
「辞めたくなった」
という声が年々増えています
なぜでしょう──
大学を選んでいないまま進学しているからです
・自分の学力でついていけるか
・学ぶ内容に興味はあるか
・キャンパスの雰囲気
どれも確認しないまま、
「推薦で行けるから」という理由だけで入学すると、入ってからミスマッチに気づくことになるのです
第2章 偏差値の低い高校ほど、指定校推薦が“落とし穴”になる理由
私立大学の6割が定員割れの状態で
最近では、偏差値の高くない高校にも、たくさんの指定校枠が来ています
これは、大学側が「定員割れを避けたい」という事情で、広く枠を開放しているためです
高校側も「大学実績をつくりたい」ため、できるだけ多くの生徒に指定校を勧めます
その結果、
生徒の学力や資質に合っていない大学でも、「枠があるから行く」というケースが生まれてしまうのです
推薦だから進学するのではなく、
「自分に合っているから進学する」
本来は、その順番のはずです
第3章 三者面談──「親の安心」で進路を決めていないか?
三者面談では、親の影響力がとても大きくなります
「指定校推薦で行けるならそれで」と親が安心してしまうと、子どもが本音を言えなくなることも
特に、「将来何がしたいかわからない」と悩んでいる生徒ほど、大人の意向に流されやすいものです
親が先回りしすぎず、子どもの意見や迷いに丁寧に耳を傾けること
子どもの特性や資質、学力などは、最も身近にいる親が一番よく理解しているはずです
子どものための“適性進路”を考える
その姿勢が、失敗のない進路選びにつながります
第4章 高校は「退学者の存在」を教えてくれない
実は、高校は「卒業生の退学情報」をほとんど公開していません
指定校推薦で進学した先輩が、その後どうなったか
辞めたのか、休学したのか──。
そうした情報が伏せられているため、「問題があるとは知らなかった」という保護者や生徒も多いのです
大学を辞めた理由としてよくあるのが、
・学びたい内容と違った
・授業についていけなかった
・友人関係に馴染めなかった
指定校推薦で進んだことが「義務」のように感じて、辞める決断も言い出せず、苦しむケースもあります
第5章 親子で“資質”と“興味”を見つめ直す時間を持とう
大事なのは、
「指定校推薦で行ける」ではなく、
その進路が、子ども自身に合っているかどうかです
・専門学校
・就職する
・本当にやりたい分野の大学を受験
いま、オープンキャンパス、学校説明会、在学生の声など、リアルな情報に触れる機会は豊富にあります
親は、「親の安心できる進学先」を探すのではなく、
子どもが“納得して選べる進路”を、一緒に考える存在ではないでしょうか
まとめ
指定校推薦は、便利な制度です
でも、それは、「大学が入学選考を高校に任せている」ということも忘れないでほしいのです
高校も、本当に「合っているか」より、大学進学実績を優先する事例が多いことも付け加えておきます
「本当にやりたい分野か」
「積極的に学ぶ習慣があるか」
見極めずに進むと、あとで本人が苦しむことになります
・大学は“行ける場所”ではなく、“学びたいことがある場所”
・指定校推薦が入れるなら大丈夫、安心して思考停止していないか
・子どもの意志や資質に向き合い、迷いを、ちゃんと聞けているか
進路選びは、すでに始まっています
高校1・2年生の今こそ、親子で「本当にそれでいいのか?」をチェックできる、最高のタイミングです
| 専門学校は都道府県の認可校です |

読者対象
最新記事
- 高校生「やりたいことがない」のではなく、「言えないだけ」かも
- Fラン退学する人、専門学校で伸びる人、子どもに合う進路とは?
- 高校1・2年生の進路選び、親子でチェック指定校推薦の”注意点”
- 指定校推薦の退学_進路指導で教えてくれない“退学者”の話
- Fラン大学進学は本人の意思次第_ 「入れればいい」は危険です
- 指定校推薦の裏側―「大学と高校」の”事情により”退学者が増加
- Fラン大量産“私大バブル”崩壊で─気づき始めた高校生と保護者
- こんなことなら、大学じゃなくて、専門学校に行けばよかった
- 指定校推薦の退学者が増加中_高校と大学の”取引”に生徒は不在
- 指定校推薦の被害「大学進学のカラクリ」─誰のための進路指導か
- 高校1年で知っておきたい“とりあえず大学”の落とし穴
- 大学辞めたい人が急増中_半期学費の支払いが生じる前に手続き
- 「とりあえず大学」の発想は本当に危うい
- 進路が決まらない高校2年生へ──あせらず出会う進路のヒント
- 大学を辞めた後「何を学べばいいかわからない」人への進路ガイド
- 大学と専門学校、オープンキャンパスで見える「親の関わり方」の違い
- 専門学校の入試_大学と違う?試験内容・時期などわかりやすく
- 将来やりたいことがない高校生へ─進路の考え方と選択のヒント
- 専門学校 入試問題レベル_難易度?勉強は必要?
- 大学中退は親泣かせ?親の気持ち_心配は当然・次どうするの?
- Fラン大学進学は、就職やキャリアに不利になる可能性がある?
- 入ってから「大学向いてない」と言う人が激増中_事前にチェック
- 大学辞めてどうする?─「次の一歩」の考え方とスケジュール
- 大学指定校推薦のデメリット_進学前に親子で確認したいこと
- 大学を辞めた後――タイプ別で見る「あなたらしい進路」
- 『大学についていけない…』と感じたら読む記事_不安・中退・留年・辛い
- 専門学校に行くメリットを、まだ誰もちゃんと教えてくれない
- 高校生したいことリスト_まとめ方のヒント
- Fラン大学行きたくない・続けられるか不安と思ったら読む記事
- ITおすすめ資格10選_初級・中級・上級
- アイリスト 資格 働きながら免許を安く_美容専門学校 通信課程
- 大学辞めた後、就職or専門学校の2択_今の実力ならどっち?
- 企業から求人オファーが来る!専門学校の就活界隈
- 氷河期世代の子供(Z世代)の君へ 「自分らしい」進路の見つけ方
- 大学中退から逆転!IT専門学校で叶える“自信と実力”の武装
- 美容専門学校「通信」・アイリストも・学費安い・昼間部との違い
- 【大学退学手続き】用紙もらい方・出し方・いつまで・親の捺印
- IT資格いらない?意味ない?業界が求めるおすすめ資格10選
- 【社会人から専門学校】手続き・お金・入試・4人に1人が社会人
- スポーツを支える・動かす仕事!!語学×ビジネスという選択肢
- 未経験でもゴールが見える専門学校━行くメリット
- 大学中退_各種証明書・単位引継ぎ━申請期限、有効期限の解説
- 子どもが大学をやめたとき_親ができること、本人ができること
- 今、”目指すのは”空港・ホテルの仕事-2年後、希望の制服を着る
- 大学中退=失敗・逃げじゃないよ!合わない道を降りるのも進路
- 大学辞めたい・合わない・退学手続き・向いてない人もいます
- 【美容師免許の取り方】最短で2年・試験内容・学校紹介
- 大学指定校推薦_うつ、退学、親の安心で子どもが苦しむことも
- “個人尊重”の時代、世界の適性進学と日本の進路の大きな違い!
- 専門学校卒が最前線で活躍しているホテル業界のリアル
- IT・情報系専門学校は意味ない?_AI時代でも意味がある理由!
- 高校をテレビに例えると進路指導は大学偏向報道じゃないの!?
- 就職氷河期世代が親として向き合う子ども(Z世代)の進路
- Fラン大・ボーダーフリー大の退学率は高い!?その背景にある要因とは
- 高校生進路希望調査【本人欄】書き方と例文
- 大学全入時代は大学入試たたき売り時代か!?年間12万人超が離脱する、ミスマッチ進学の代償
- 指定校推薦で入った大学を退学する際の注意点・謝罪は必要?
- 子どもたちの「できた!」がやりがい_感動の毎日 保育士・幼稚園教諭
- 【通信制 専門学校】どんな学び方?分野・資格・学校紹介
- 偏差値30台40台から大学指定校推薦の注意点
- 最高の1日を演出する ホテル・ブライダル・美容師・アイリスト
- 特色ある学科・学び方の専門学校
- アイリスト資格は美容師免許!最短2年マツエクも美容専門学校
- 大学と専門学校の違い・就活の違い
- 専門学校面接対策:よくある質問、回答例、好印象マナーを解説
- 高校生進路希望調査【保護者欄】書き方と例文
- 専門学校卒業 学歴は【専門学校卒】_「学歴に入らない」は誤り
- 大学辞めたい 親に言えない
- 「大学中退の最終学歴」は高校卒業・履歴書は「中途退学」と記載
- 専門学校の入学方法_入試の種類・入学資格・入学までの流れ
- フリーターから専門学校のメリット・確認点をわかりやすく紹介
- 専門学校のオープンキャンパス何する?
- 子供が「大学を辞めたい」_親の気持ち・何を伝える・次どうする
- 子どもの「大学辞めたいサイン」見逃していませんか?
- 高校生の進路選びで親のできること
- 専門学校「保護者の意見欄」書き方・例文
- 高校の進路指導は高校生にリスク!? 大学退学者が増えている背景
- 「大学に入れば何とかなる」は幻想です
- 専門学校の志望理由書 書き方・例文
- Fランク大学と専門学校どっちがいい?将来性は?