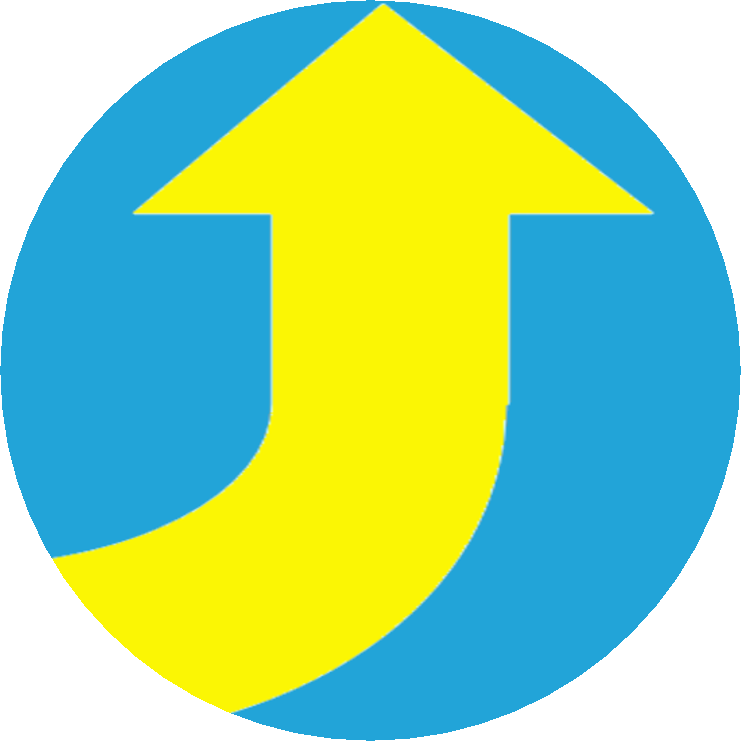はじめに──選ばない大学、選ばせない高校
指定校推薦は、高校の推薦によって大学に入学できる仕組みです
一見、「高校で真面目に取り組んだ生徒を評価する制度」にも見えますが
本来、大学が責任を持って行うべき入学選考を、高校に丸投げしている側面があることは、あまり語られていません
大学は、生徒一人ひとりの詳細まで見て合否を決めるわけではありません
そのため、実質的に「入学者を選ばない」状況です
高校は、生徒一人ひとりの資質を優先した進路指導でなくなっている例も
そのため、大学に誘う「選ばせない進路指導」も存在します
この問題の背景には、次の“三つ巴”があります
1.私立大学の6割が定員割れの状態
・大学は、「定員を埋めるために推薦枠を拡大」し
2.偏差値の低い高校でも、大学進学実績を作りたい
・高校は「とにかく大学に送り出すこと」が目的になり
3.できれば子どもを大学に行かせたいと願う保護者
・子どもの適性より「大学に行けるなら」という安心を優先
「提示された大学に行く」だけの存在になってしまう
この三要素が、絶妙のバランスで保たれてきたのが、指定校推薦枠の実態です
指定校推薦の裏にある「進学取引」でバランスが崩壊
そんな、複雑な進学構造と心理が“進学取引”を生み出しています
高校と大学の間で交わされる“指定校推薦”は、
本来は「相性の良い生徒を推薦する仕組み」のはずでした
しかし今は、
・大学は、
定員割れを避けるため、“取引先である高校の枠”をどんどん広げる
・高校は、
取引先である大学の進学実績を増やすため、“要望に応えて”生徒を送り出すという“取引関係”になってしまっています
それでも、これまでは何とかバランスが保たれてきましたが、“人数合わせ”の進学は限界点を超えてしまいました
ついにバランスが保てなくなり、退学者が増える結果となってしまいました
置き去りにされている、生徒と保護者
そもそも、勉強が得意なわけでもなく、学びたい分野も見つかっていない生徒が、
三者面談などをきっかけに
「大学に行けるのか」と“進学の夢”を見せられ、
これまで具体的ではなかった大学進学を目指してしまう
でも、その夢は「誰かの数字のために作られた幻想」だった──。
進学した結果…
大学に入ってから、
「なんか違う」
「講義がつまらない」
「意味がわからない」
「行く意味ある?」
そう思っても、もう後戻りできない。
そして、最悪の結末──退学
こんなことが毎日、数えきれないほど起こっています
「指定校推薦で進学したけど、やめたい」が急増中
最近、指定校推薦で大学に入学したものの、早々に退学を選ぶ学生が増えています
中には、入学から半年も経たないうちに「もう無理かも」と感じる人も
これは、高校と大学、そして保護者の“思惑”が生んだ構造的な問題なのです
退学者は“本人のせい”だけではない“ある意味で被害者”
こうして退学した学生の中には、
「自分が悪かったのかも」と責める人もいます
でも、そうした構造に巻き込まれてしまった時点で、ある意味では“被害者”でもあるのです
もし、指定校推薦がなかったら──
もし、「合っているか」をちゃんと見極めていたら──
もしかすると、その大学には進学しなかったかもしれません
誰かが生徒の立場を考えていれば、止められたルート
・大学が推薦枠を安易に広げなければ
・高校が大学進学実績の数字さえ追わなければ
・親が“大学ありき”で判断しなければ
生徒が無理に大学に行く必要はなかったかもしれません
じゃあ、どうしたらいいのか?
この構造を止めるには、保護者と本人の意識の変化が必要です
保護者は、
・子どもが「大学向き」かどうか、本気で見極める
・「とりあえず大学」は、本人のためにならないと理解する
・「誰でも大学に行く時代」の中でも、自分たちは“考えて進学する”と決める
高校生本人も、
・「やりたいことはあるか」
・「続けられそうな分野か」
・「実習が多い専門学校の方が向いているのでは?」
といった視点で、自分自身と向き合う必要があります
進学先の決定に「本人」が不在では、続かない
指定校推薦そのものを否定するわけではありません
でも、そこに生徒本人がいないまま“枠”や“実績”だけで進学が決まるのは、やはりおかしい
進学とは、その先を自分で歩けるかどうかがいちばん大事です
「高校と大学の関係性」ではなく、
「子ども自身の意思と特性」を軸に、進学を見直すタイミングが来ています
| 専門学校は都道府県の認可校です |

読者対象
最新記事
- 高校生「やりたいことがない」のではなく、「言えないだけ」かも
- Fラン退学する人、専門学校で伸びる人、子どもに合う進路とは?
- 高校1・2年生の進路選び、親子でチェック指定校推薦の”注意点”
- 指定校推薦の退学_進路指導で教えてくれない“退学者”の話
- Fラン大学進学は本人の意思次第_ 「入れればいい」は危険です
- 指定校推薦の裏側―「大学と高校」の”事情により”退学者が増加
- Fラン大量産“私大バブル”崩壊で─気づき始めた高校生と保護者
- こんなことなら、大学じゃなくて、専門学校に行けばよかった
- 指定校推薦の退学者が増加中_高校と大学の”取引”に生徒は不在
- 指定校推薦の被害「大学進学のカラクリ」─誰のための進路指導か
- 高校1年で知っておきたい“とりあえず大学”の落とし穴
- 大学辞めたい人が急増中_半期学費の支払いが生じる前に手続き
- 「とりあえず大学」の発想は本当に危うい
- 進路が決まらない高校2年生へ──あせらず出会う進路のヒント
- 大学を辞めた後「何を学べばいいかわからない」人への進路ガイド
- 大学と専門学校、オープンキャンパスで見える「親の関わり方」の違い
- 専門学校の入試_大学と違う?試験内容・時期などわかりやすく
- 将来やりたいことがない高校生へ─進路の考え方と選択のヒント
- 専門学校 入試問題レベル_難易度?勉強は必要?
- 大学中退は親泣かせ?親の気持ち_心配は当然・次どうするの?
- Fラン大学進学は、就職やキャリアに不利になる可能性がある?
- 入ってから「大学向いてない」と言う人が激増中_事前にチェック
- 大学辞めてどうする?─「次の一歩」の考え方とスケジュール
- 大学指定校推薦のデメリット_進学前に親子で確認したいこと
- 大学を辞めた後――タイプ別で見る「あなたらしい進路」
- 『大学についていけない…』と感じたら読む記事_不安・中退・留年・辛い
- 専門学校に行くメリットを、まだ誰もちゃんと教えてくれない
- 高校生したいことリスト_まとめ方のヒント
- Fラン大学行きたくない・続けられるか不安と思ったら読む記事
- ITおすすめ資格10選_初級・中級・上級
- アイリスト 資格 働きながら免許を安く_美容専門学校 通信課程
- 大学辞めた後、就職or専門学校の2択_今の実力ならどっち?
- 企業から求人オファーが来る!専門学校の就活界隈
- 氷河期世代の子供(Z世代)の君へ 「自分らしい」進路の見つけ方
- 大学中退から逆転!IT専門学校で叶える“自信と実力”の武装
- 美容専門学校「通信」・アイリストも・学費安い・昼間部との違い
- 【大学退学手続き】用紙もらい方・出し方・いつまで・親の捺印
- IT資格いらない?意味ない?業界が求めるおすすめ資格10選
- 【社会人から専門学校】手続き・お金・入試・4人に1人が社会人
- スポーツを支える・動かす仕事!!語学×ビジネスという選択肢
- 未経験でもゴールが見える専門学校━行くメリット
- 大学中退_各種証明書・単位引継ぎ━申請期限、有効期限の解説
- 子どもが大学をやめたとき_親ができること、本人ができること
- 今、”目指すのは”空港・ホテルの仕事-2年後、希望の制服を着る
- 大学中退=失敗・逃げじゃないよ!合わない道を降りるのも進路
- 大学辞めたい・合わない・退学手続き・向いてない人もいます
- 【美容師免許の取り方】最短で2年・試験内容・学校紹介
- 大学指定校推薦_うつ、退学、親の安心で子どもが苦しむことも
- “個人尊重”の時代、世界の適性進学と日本の進路の大きな違い!
- 専門学校卒が最前線で活躍しているホテル業界のリアル
- IT・情報系専門学校は意味ない?_AI時代でも意味がある理由!
- 高校をテレビに例えると進路指導は大学偏向報道じゃないの!?
- 就職氷河期世代が親として向き合う子ども(Z世代)の進路
- Fラン大・ボーダーフリー大の退学率は高い!?その背景にある要因とは
- 高校生進路希望調査【本人欄】書き方と例文
- 大学全入時代は大学入試たたき売り時代か!?年間12万人超が離脱する、ミスマッチ進学の代償
- 指定校推薦で入った大学を退学する際の注意点・謝罪は必要?
- 子どもたちの「できた!」がやりがい_感動の毎日 保育士・幼稚園教諭
- 【通信制 専門学校】どんな学び方?分野・資格・学校紹介
- 偏差値30台40台から大学指定校推薦の注意点
- 最高の1日を演出する ホテル・ブライダル・美容師・アイリスト
- 特色ある学科・学び方の専門学校
- アイリスト資格は美容師免許!最短2年マツエクも美容専門学校
- 大学と専門学校の違い・就活の違い
- 専門学校面接対策:よくある質問、回答例、好印象マナーを解説
- 高校生進路希望調査【保護者欄】書き方と例文
- 専門学校卒業 学歴は【専門学校卒】_「学歴に入らない」は誤り
- 大学辞めたい 親に言えない
- 「大学中退の最終学歴」は高校卒業・履歴書は「中途退学」と記載
- 専門学校の入学方法_入試の種類・入学資格・入学までの流れ
- フリーターから専門学校のメリット・確認点をわかりやすく紹介
- 専門学校のオープンキャンパス何する?
- 子供が「大学を辞めたい」_親の気持ち・何を伝える・次どうする
- 子どもの「大学辞めたいサイン」見逃していませんか?
- 高校生の進路選びで親のできること
- 専門学校「保護者の意見欄」書き方・例文
- 高校の進路指導は高校生にリスク!? 大学退学者が増えている背景
- 「大学に入れば何とかなる」は幻想です
- 専門学校の志望理由書 書き方・例文
- Fランク大学と専門学校どっちがいい?将来性は?