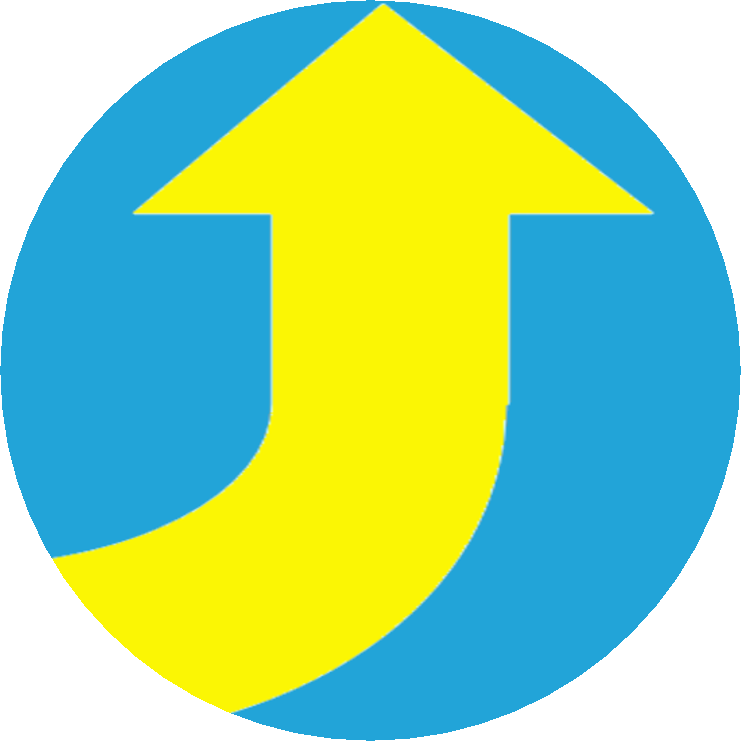はじめに:投票率上昇の背景にある「本能的なノー」
2025年、10代(特にZ世代)の投票率が上昇しました。ただし、これは政治への関心の高まりというより、もっと身近にある危機感からくる“生きる本能”の反応と考える方が自然です
彼らは「何かがおかしい」と感じ、それに対して自ら意思表示する動きを始めています
「おかしいことにはノーと言う」
この忘れていた当たり前のことを、
今、Z世代は自らの行動で証明しています

1. 親世代が見落としてきた30年間の構造的変化
18歳人口の激減・大学数の増加
| 30年前と比較 | 1995年(30年前) | 2025年(現在) |
| 18歳人口 | 約205万人 | 約110万人(半減) |
| 大学数 | 約570校 | 約800校(1.4倍に) |
進学率の上昇と受け皿のひずみ
18歳人口は減り続ける中で、無計画に私立大学を設置し続けた結果、受け皿(大学)が過剰となり、多くの大学が定員割れを起こす事態となっています
2. 身近な違和感から社会へ広がる危機意識
10代はすでに、自分たちに身近な「学校」「進学制度」の矛盾に気づき始めています
指定校推薦など「試験を受けなくても大学に行けてしまう」ことなど、「自分たちが気づかないまな、何かに流されている」ような違和感です
学校や進学だけでなく、次第に「就職」「社会」「将来」「平和」といった広い視野にまで危機意識は広がっていくでしょう
“あまり意思表示をしない”と見られていた彼らの「おとなしさ」は、むしろ研ぎ澄まされた感覚の裏返しかもしれません
3. 「親の世代とは違う」Z世代の意思表示=30年越しの再起動
親世代が当たり前と思っていた常識、そして「仕方ない」と諦めていた構造的な問題に対し、Z世代は自分たちの意思で「ノー」と言える権利を持っています
ですが、学生の立場では、
権利はあっても力がない…..
その中で、静かな抵抗とも言えるこの動きが、保護者の決裁ではなく自分で決めることができる“選挙の投票”という形で表面化してきていると見ています
今に対する「ノー」
学校や進学にとどまらず、次は社会全体に対してノーを示す段階へと移行する可能性が高いでしょう
まさに、30年止まっていた日本の成長に、10代という世代が「再起動」のきっかけを与えるかもしれません
そして、それは、今の高校生たちが
自らの意思で「将来を選ぶ」権利と力を持ち始めたことに他なりません
4. 結び—「常識の上書き」が始まっている
親世代の「常識」は子どもにとって必ずしも妥当なものではなくなりました
18歳人口が激減し、大学数が増え「希望すれば大学に入れる」。その構造の矛盾を前に、Z世代は「違和感」を直感として捉え、自らの意思で未来を選び始めています
その動きは、投票率という、一見すると無関係に思われる行動ですが、
Z世代が「自らの意思で行動」したことに価値があり、数字に現れた「本能的なノー」は、日本社会に対する鋭い生命反応といえるでしょう
とはいえ、18歳では、特に進学など保護者の意向が色濃く出る場面では「つい抑制的な反応」をしてしまうことが十分考えられます
ですから、保護者の立場としては、「子どもの本能」をどのように察知し、どう対応するかが、今、問われているのです
大学に行くことだけが、進路の正解じゃありません。「何を学ぶか」「どう働きたいか」から考えると、『とりあえず』ではなく『本気で』学ぶ意味も見えてきて、専門学校のほうが合う人もたくさんいます。どんな分野があるのか見てからでも遅くありません。
あなたに合った専門学校がみつかるかもしれません。
| 専門学校は都道府県の認可校です |

読者対象
最新情報
- 専門学校卒業生のここがいい─企業が評価する即戦力の実態とは
- 「IT専門学校は意味ない」と言われる理由と”実際のところ”を解説
- AI時代にIT専門学校って意味ない?→企業の答えは真逆だった
- 大学卒業後→専門学校
- 大学誰でも入れる時代|「入れる」と「続けられる」は別の話
- 大学辞めてよかった。やっと眠れるようになった
- 社会人から美容師になるには
- 社会人から臨床工学技士になるには
- 社会人から理学療法士になるには
- 大学中退から保育士になるには
- 子供が大学を辞めることになる前に
- 「ありがとう」が聞こえる仕事へ。専門学校という選択
- 大学行きたくない 親に言えない
- 社会人から保育士になるには
- 「売り手市場」でも、やりたい仕事に就けるとは限らない!?
- 知らない人が結構多い!?専門学校AO入学エントリーに関する誤解
- 高校生の進路「早期内定」には要注意_複数校を比較して決めよう
- 「大学やめたい」「大学ついていけない」人がホントに多いんです
- 専門学校はメンタルとモチベ-ションを支える伴走型の環境です
- 大学受験に失敗しても専門学校という選択肢、大学編入制度も
- 大学卒業後に専門学校を卒業した人_最終学歴は【大学卒】です
- 「進路 親のいいなり」―あなたの人生の”主役”は誰ですか?
- 大学中退から専門学校|卒業時は「新卒採用+スカウト型」就活
- 知らないと損 ハローワーク経由で “安く”保育士資格を取る制度
- 社会人から保育士に!専門学校で学ぶメリットと支援制度
- 内閣支持率「若者の価値観の変化」そこから見える進路のカタチ
- Fラン大・事実上無試験大の学生は企業からどう見られている?
- 経営悪化の私立大学に文科省が指導強化―価値のある進学とは?
- 親が進路を考えてくれない_どういう事?どうしたらいい?
- 専門学校は本当に楽しい?前向きの理由は在校生が感じる充実感
- 通信制専門学校_自分時間と両立し「資格・スキルを身につける」
- 大学の年内学力入試で進む、新たな「大学ミスマッチ」!?
- 行く価値のある専門学校とは?分野選びの指針と考え方
- 大学中退 親の気持ち
- 年内学力入試の導入で、「Fラン vs 専門学校」はもう古い考え方
- 年内学力入試が増えると、Fラン大学が見えにくくなる!?
- 専門学校に偏差値はある?知っておきたい入試の仕組み
- 大学年内入試拡大で専門学校の価値が上昇するこれだけの理由
- 「学びたい学生を迎えたい専門学校」と「人を集めたい大学」の違い
- AI時代に「とりあえず大学」「どこかに就職」の感覚じゃダメ
- ホテルで働きたい_方法はいくつかあります
- 社会人から専門学校へ_不安要素を解決!完全ガイド&学校紹介
- 大学を中退して専門学校へ_新たなスタートが生む自信と未来
- 大学中退後の3つの道:今すぐ中途採用・新卒正社員・公務員も
- 大学の年内学力入試が進む一方で──注目したい専門学校の実力
- AIで仕事はどうなる?高校生のための進路とキャリアガイド
- オールドメディアが報じない「専門学校」の実力こそ本当はスゴイ
- 大学中退 人生終了 今は辛い気持ちでも、必ず立ち直れます
- 子どもが大学を辞めたいと言ったら_専門学校で2年後正社員に
- リハビリの仕事に就くには:理学療法士と作業療法士の違いと、キャリアの選び方
- 「公務員になってほしい」保護者へ_各省庁に強い語学専門学校
- 理学療法と作業療法は何が違う?_やりたいリハビリはどっち?
- 大学中退は終わりじゃない。2年で「企業が欲しがる人材」になる
- ホテル専門学校に行く意味ある?―意味もあれば価値もあります
- ホテル専門学校って厳しい?ホテル業界はこんなに変化している
- 医療現場をテクノロジーで支える仕事— 臨床工学技士とは?
- 保育士を目指す大学と専門学校の違い、どっちがおすすめ?
- 映像クリエイターを目指す専門学校_きっと観てる“実写”映像
- AI時代のIT業界の目指し方_大学? 専門学校? 選び方完全ガイド
- 特色ある学科・学び方の専門学校
- 指定校推薦で大学中退した子どもへ – 親ができるサポートとは
- 「なんとなく大学」合わずに中退_仕事観で出会えた専門学校
- 高校生の子供が進路を迷っている、親はどう対応すればいい?
- 「就職ミスマッチ」は避けられる!? 専門学校=業界付属校の強み
- 大学中退から専門学校「再スタート迷子」にならない進路の選び方
- Fラン大と専門学校どっちがいい? そもそも「次元が違う」話
- 高校卒業してからじゃ遅いんです_就活迷子にならない進路選び
- 専門学校の就活は「スカウト型」_大学の就活は「売り込み型」
- 専門学校のいいところが今の高校生に合っている7つの理由
- 大学中退は親泣かせ?親の気持ち_心配は当然・次どうするの?
- 高校1・2年生の進路選び、親子でチェック指定校推薦の”注意点”
- Fラン中退する人、専門学校で伸びる人、子どもに合う進路とは?
- 指定校推薦の退学者が増加中_高校と大学の”取引”に生徒は不在
- Z世代の再起動=親世代に定着した「常識」の上書きが始まった
- 氷河期世代の子供(Z世代)の君へ 「自分らしい」進路の見つけ方
- 指定校推薦デメリット_大学進学前に親子で確認したいこと
- 専門学校に行こうよ
- 未経験でもゴールが見える専門学校_行くメリット
- 「いい大学じゃないと、いい会社には入れない」は本当?実はね!
- 大学ミスマッチの先に見え隠れする就職ミスマッチ・退職代行