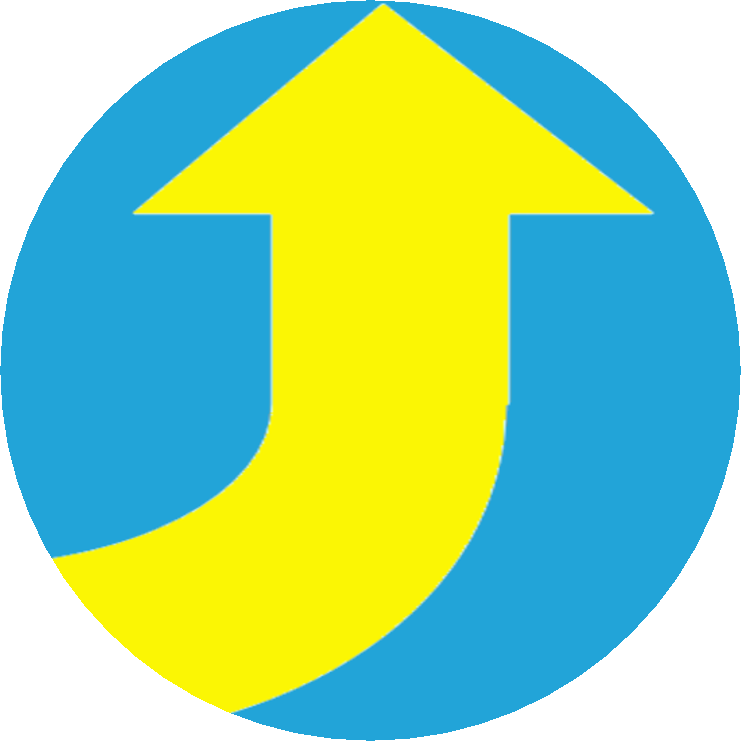一緒に考えてあげることが、最大の支援
進路選びはお子様にとって大きな挑戦ですが、保護者としてできることはたくさんあります
お子様と一緒に考え、悩み、そして喜びを分かち合いながら、納得のいく進路を見つけてあげてください
1.一緒に考える
- お子さんの希望や考えを聞く:
お子様の希望や考えをじっくりと聞き、尊重しましょう。頭ごなしに否定するのではなく、まずは受け止めることが大切です
- 一緒に進路について話し合う:
お子様と一緒に進路について話し合いましょう。それぞれの選択肢のメリット・デメリットを整理したり、将来の目標やライフプランを考えたりするのも良いでしょう
- お子様の考えを整理する手伝いをする:
お子様の考えがまとまらない場合は、質問をしたり、情報を整理したりする手伝いをしましょう
2.情報収集と整理
- 進路に関する情報を集める:
お子様の意思、資質を踏まえて、大学、専門学校、就職など、様々な選択肢に関する情報を集め、お子様に提供しましょう。インターネット、書籍、資料請求、学校説明会、オープンキャンパスなど、様々な情報源を活用できます
- お子様の興味や関心に合わせた情報を提供する:
お子様の興味や関心に合わせた学校、学部、学科、職業に関する情報を集め、共有しましょう
- 進学候補の学校に相談する:
複数の学校で同じ質問を投げかけてみることも問題の整理と解決につながることもあります。
たとえば「消極的でクラスの人間関係を上手くやっていけるか心配」など
「本当に心配なこと」「不安なこと」に対して回答を得ることができます。
何がお子様に必要か比較することができます
3.応援とサポート
- お子様の選択を尊重する:
お子様が最終的にどのような選択をしたとしても、尊重し、応援しましょう
- 精神的なサポートをする:
進路選択の時期は、お子様にとって大きなプレッシャーがかかる時期でもあります。精神的なサポートを心がけ、励ましの言葉をかけたり、話を聞いてあげたりしましょう
「いつも味方であること」「常に信じていること」を言葉で伝えましょう
子どもにとってこれ以上、自信と勇気をもらえることはありません
- 経済的なサポートをする:
進学には費用がかかります。経済的なサポートも検討しましょう。修学支援新制度、学費分納なども調べてみましょう
- 具体的な行動をサポートする:
受験対策、面接練習、願書提出など、具体的な行動をサポートしましょう
4.親自身の考えを見直す
- 親の価値観を押し付けない:
親自身の価値観や考えを押し付けるのではなく、お子様の考えを尊重しましょう
- 過度な期待をしない:
過度な期待は、お子様のプレッシャーになります。お子様のペースに合わせて、無理のない目標設定をしましょう
- 情報過多に注意する:
情報過多は、お子様を混乱させる原因になります。必要な情報を整理し、シンプルに伝えましょう
5.進路は変化するものとお互い理解
- 進路は途中で変わる可能性もある:
進路は一度決めたら終わりではありません。途中で変わる可能性もあることを理解しておきましょう
- 人生は人それぞれ:
高校から大学に進学したものの環境が合わず退学する人もいます。大卒で就職した人の34.9%が入社3年以内に離職しています。高校卒で就職して何年か後に専門学校に入学する人もいます
- 変化を受け止める気持ちを養う:
変化を受け止めることも大切です。様々な経験は決して無駄にはならないこと、柔軟な考え方があるということを共有するのも必要です
どの道に進んでも、乗り越えなければならないことはあります
そのことを親御さんはご存じのはずです
どの道に進んでも、その場所をどう捉えて、何をするかが一番大切です
お子様の将来について一緒に考えて、理想に沿った選択ができるよう応援しています
「仕事観」で考えたら進路が見えた
| 「仕事観」で、就職・再進学が明確に ・どの業界で働きたいのか ・どのような職種に興味があるのか ・自分の強みや興味は何なのか ・どんなことなら続けられそうか ●高卒学歴で就職できる仕事はありますが ●資格・スキルで新卒就職なら、専門学校 | |
| 気持ちの切り替え | うつ状態を感じたらまずは、「内科」で大丈夫 かかりつけのお医者さんに相談できます |
| 学歴はどうなる? | 大学中退の学歴は「高校卒」 専門学校の学歴は「専門学校卒」です 履歴書にも書けます |
| 大学編入もできる | 専門学校卒は、大学に編入も可能です(3年or2年) |
| 学費について | 専門学校でも、学費の分割が可能です(半期、毎月など) ※奨学金の再利用可(専門学校で手続) |
| 雰囲気と授業 | 専門学校は4人に1人が大学中退・社会人など「高校既卒者」 授業のすすめ方は、高校に近いイメージ |
| 資格・スキル・就職 | 国家資格、技術、を最短で効率よく修得できます 学生1名に十社以上「オファー」が届くスカウト型の就活 |
| どの分野がいい? | 未経験でも大丈夫、気になる分野は、学校見学をおすすめ 高校卒で採用してもらえるなら、就職する道も進路です |
| 専門学校は都道府県の認可校です |

資料請求(無料)
※個人情報の取り扱いは安心です
2026入学 特典あり 入学準備はお早めに
高校生は三者面談の準備にもなります
1.無料で取り寄せ・比較できる
資料請求をすると学校資料を無料で入手できます
パンフレット一式は郵送(宅配)でご自宅に届きます
※お手元で資料を広げて見ることができます
・学校パンフレット
・募集要項
・オープンキャンパス日程、などです
2.公式サイトより見やすく詳しい
公式サイトはスマホでも見ることができますが、パンフレットは公式サイトよりも見やすいのが特色です
また、スマホではサッと比較しにくい他校との違いも簡単にわかります
気になることや、詳しく聞いてみたいことなどがあればオープンキャンパスなどでご確認ください
3.説明会の年間スケジュール
学校資料には、説明会・オープンキャンパスの年間スケジュールが同封されています
公式サイトにも日程は掲載されていますが、1ヵ月以内の日程を掲載していることが多くなっています
たとえば「夏休み前までに3校訪問する」として、保護者と同伴する場合など「先の予定を立てる」のに役立ちます
4.高校生は三者面談の準備に
高校で行う保護者も交えた三者面談では、進学希望の学校についても意見交換します
事前に保護者にも見てもらうことで、学校についての理解と、より詳しい情報を共有できます
三者面談の準備をする意味でも、パンフレットが手元にあると便利です
オープンキャンパス(説明会・相談・体験)
※個人情報の取り扱いは安心です
2026入学 参加特典あり 入学準備はお早めに
過去の試験問題・作文課題も入手できる
1.参加特典がある
多くの専門学校で「参加特典」があります。以下は一例です
入学選考の優遇
AO入試や推薦入試の受験資格が得られたり、面接や書類選考で加点されたりする場合があります
学費の減免
入学金や授業料の一部が免除される制度を設けている学校があります
選考料の免除
多くの専門学校では、オープンキャンパスや体験入学に参加した人に対して、入学選考料を免除する制度を設けています
2.過去の試験問題・作文課題も
入試で「筆記試験」を実施する学校もありますが「過去の問題集」や「作文の課題」は事前に公開されています
オープンキャンパス(学校説明会)では、AO入学のエントリー方法をはじめ、入試に関する説明、「過去の問題集」「作文の課題」についても情報を入手することができます
3.学校の雰囲気を感じられる
学生はどんな様子か?
校舎や設備も気になると思いますが、学校全体の空気感を感じてください!
参加者の40%は保護者同伴です
当日は「保護者説明会」を開催する学校もあるので、子どもは体験、保護者は学校説明など、時間を有効に使うことができます
4.自分もやれそうな気持ちに
行きたい分野の専門学校のオープンキャンパスに参加した後は、目標が一層はっきりするようです
先輩や先生の話を直接聞いて「自分でもやれそうな気持ちになる」人が多いとお聞きしています
在校生の話を聞ける機会もあります
先生と学生の距離感や2年後こんなに成長できるんだ!と実感することができます
修学支援新制度
世帯収入に応じて3段階
返済の必要のない学費支援
給付型奨学金+入学金・授業料の免除、減免
高校生の場合は、高校を通じて日本学生支援機構(JASSO)に申し込むので分かりやすいと思います
・給付型奨学金は
進学する前年の4月下旬から申込ができます
・入学金+授業料 免除、減免は
入学時に、進学先の専門学校に申し込みます
※子どもが3人以上の家庭の場合
2025年度から、これとは別に多子家庭を対象に無償化制度が導入されます。第1子が卒業後就職をして扶養を抜けると第2子、第3子は対象から外れます
学費分納あり
学費を分けて納付する制度
学校ごとに、学費の分納制度を設けています。
1年間の学費を一括納入ではなく、半期単位、3ヵ月単位、月ごとに納付ができる制度です。
納付期日は、各校ごとに定められているので、各学校でお確かめください。
すべての方が対象です
学費分納制度は、専門学校に入学する全ての方を対象にしています。
高校生、大学中退者、フリーランス、社会人、どなたでも対象になる経済的な支援制度として好評です。
読者対象
最新情報
- 内閣支持率「若者の価値観の変化」そこから見える進路のミカタ
- Fラン大・事実上無試験大の学生は企業からどう見られている?
- 経営悪化の私立大学に文科省が指導強化―価値のある進学とは?
- 親が進路を考えてくれない_どういう事?どうしたらいい?
- 専門学校は本当に楽しい?前向きの理由は在校生が感じる充実感
- 通信制専門学校_自分時間と両立し「資格・スキルを身につける」
- 大学の年内学力入試で進む、新たな「大学ミスマッチ」!?
- 行く価値のある専門学校とは?分野選びの指針と考え方
- 大学中退 親の気持ち
- 年内学力入試の導入で、「Fラン vs 専門学校」はもう古い考え方
- 年内学力入試が増えると、Fラン大学が見えにくくなる!?
- 専門学校に偏差値はある?知っておきたい入試の仕組み
- 大学年内入試拡大で専門学校の価値が上昇するこれだけの理由
- 「学びたい学生を迎えたい専門学校」と「人を集めたい大学」の違い
- AI時代に「とりあえず大学」「どこかに就職」の感覚じゃダメ
- ホテルで働きたい_方法はいくつかあります
- 社会人から専門学校へ_不安要素を解決!完全ガイド&学校紹介
- 大学を中退して専門学校へ_新たなスタートが生む自信と未来
- 知らないと損 ハローワーク経由で “安く”保育士資格を取る制度
- 大学中退後の3つの道:今すぐ中途採用・新卒正社員・公務員も
- 大学の年内学力入試が進む一方で──注目したい専門学校の実力
- AIで仕事はどうなる?高校生のための進路とキャリアガイド
- 社会人から保育士に!専門学校で学ぶメリットと支援制度
- オールドメディアが報じない「専門学校」の実力こそ本当はスゴイ
- 大学中退 人生終了 今は辛い気持ちでも、必ず立ち直れます
- 子どもが大学を辞めたいと言ったら_専門学校で2年後正社員に
- リハビリの仕事に就くには:理学療法士と作業療法士の違いと、キャリアの選び方
- 「公務員になってほしい」保護者へ_各省庁に強い語学専門学校
- 理学療法と作業療法は何が違う?_やりたいリハビリはどっち?
- 大学中退は終わりじゃない。2年で「企業が欲しがる人材」になる
- ホテル専門学校に行く意味ある?―意味もあれば価値もあります
- ホテル専門学校って厳しい?ホテル業界はこんなに変化している
- 医療現場をテクノロジーで支える仕事— 臨床工学技士とは?
- 保育士を目指す大学と専門学校の違い、どっちがおすすめ?
- 映像クリエイターを目指す専門学校_きっと観てる“実写”映像
- AI時代のIT業界の目指し方_大学? 専門学校? 選び方完全ガイド
- 特色ある学科・学び方の専門学校
- 指定校推薦で大学中退した子どもへ – 親ができるサポートとは
- 「なんとなく大学」合わずに中退_仕事観で出会えた専門学校
- 高校生の子供が進路を迷っている、親はどう対応すればいい?
- 「就職ミスマッチ」は避けられる!? 専門学校=業界付属校の強み
- 大学中退から専門学校「再スタート迷子」にならない進路の選び方
- Fラン大と専門学校どっちがいい? そもそも「次元が違う」話
- 高校卒業してからじゃ遅いんです_就活迷子にならない進路選び
- 専門学校の就活は「スカウト型」_大学の就活は「売り込み型」
- 専門学校のいいところが今の高校生に合っている7つの理由
- 大学中退は親泣かせ?親の気持ち_心配は当然・次どうするの?
- 高校1・2年生の進路選び、親子でチェック指定校推薦の”注意点”
- Fラン中退する人、専門学校で伸びる人、子どもに合う進路とは?
- 指定校推薦の退学者が増加中_高校と大学の”取引”に生徒は不在
- Z世代の再起動=親世代に定着した「常識」の上書きが始まった
- 氷河期世代の子供(Z世代)の君へ 「自分らしい」進路の見つけ方
- 指定校推薦デメリット_大学進学前に親子で確認したいこと
- 専門学校へ行こうよ
- 未経験でもゴールが見える専門学校_行くメリット
- 「いい大学じゃないと、いい会社には入れない」は本当?実はね!
- 大学ミスマッチの先に見え隠れする就職ミスマッチ・退職代行
- 高校卒業後どうする?どうしたい?で、悩んでいるあなたへ
- Fラン大に進学したら「まわりが驚くほどやる気がない」は本当?
- 指定校推薦で、「うまくいった人」「失敗した人」に学ぶヒント
- 高校2年で進路が決まっていないけど、何か問題ありますか?
- 「専門学校意味ない」は間違い──そう言えるのは実力のある人
- 評価は学歴から学習歴へ─人材採用が進化する「令和の真価論」
- 大学のオープンキャンパスで見た、親子のリアルなすれ違い
- 親に進路を反対されたらどうする?
- 学部が決められないのに大学進学?─進路の矛盾に気が付いた
- 学歴にこだわる親をどう説得する?親の理解と子供の進路戦略
- 「大学中退 人生終了 人生詰んだ」─そんなことは絶対ないです
- 「なんちゃって学歴」は通用しない_「学習歴、体験歴」の時代へ
- Fラン大vs専門学校_選ぶ前に考える「卒業してなんぼ」の視点
- 専門学校で開花する「生きる力」─自信・責任感・自立心
- 指定校推薦ついていけない─大学生も高校生も「選び直す」自分
- 指定校推薦で大学中退も─後悔しないための専門学校という選択
- 大学中退は「終わり」じゃない──専門学校で広がる可能性
- 高校進路指導の問題点──それって進路ガチャじゃないの?
- 指定校推薦で大学、退学_次こそ自分で決断する“本当の進路”
- 進路は自分で決める!指示待ち人間 にならないための第一歩
- 選んだつもりで選ばされている大学進学になっていませんか?
- 専門学校はいつまで入れる?知らないと損する、手続きの時期
- 高校生「やりたいことがない」のではなく、「言えないだけ」かも