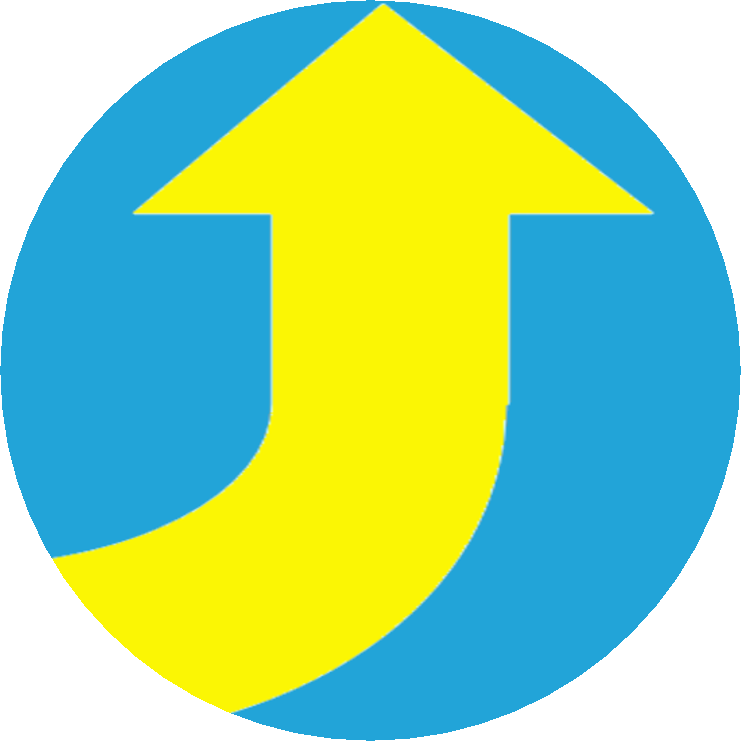1. 「とりあえず大学」は、高校時代の「ボタンの掛け違い」
多くの高校生が「とりあえず大学」の選択をする背景には、「大学へ行くのが当たり前」という高校の進路指導、大学指定校推薦の拡大、保護者の意向などがあります。
さらに、「将来やりたいことが見つからないから、とりあえず大学で考える」という“決められない”思考も同居しています。
しかし、この選択は、その後の人生に大きな影響を与える「ボタンの掛け違い」となる可能性があります。
高校時代に、仕事観、人生観を全く考えず、「大学に行けるから」という理由で進学した結果、さまざまな問題が起きています
- 目的意識の欠如: 何をその大学で学ぶのか、という目的が明確でないため、入学後の学習意欲が低下し、本来の学生生活を送ることが難しくなる。
- 専門分野への不適合: 与えられた中から選んだ大学・学部が、自身の興味や適性に合わず、大学での学習内容に苦痛を感じる。
- 居場所がなく退学者が増加: 入学してから、大学に合わない、思ってたのと違うと気づき、退学者が増えていることが問題になっています。
- 将来のキャリア像の曖昧さ: 専門性が乏しい学部・学科の場合、将来どのような仕事をしたいのかが定まらないまま、就職活動を迎え苦戦する。
2. 就職ミスマッチと退職代行の増加
高校時代からの「ボタンの掛け違い」は、「大学ミスマッチ」を経て、「就職ミスマッチ」へと繋がります。特にFラン大学の学生が直面する「売り込み型就活」は、この問題を鮮明に映し出しています。
大学の「売り込み型就活」: 学生自ら企業を探し、1社づつエントリーするスタイルです。大手企業には「大学フィルター」がありますし、中堅・中小企業にも、「やりたいこと」「何ができるか」を明確に言語化し、自身を売り込む必要があります。しかし、「とりあえず大学」で入学した学生にとって、これは極めて困難な作業となる場合があります。
- 企業研究の浅さ: ジャンルを越えて多くの企業に手当たり次第エントリーする傾向があり、深い企業研究や自己分析が不十分なまま選考を迎えてしまう。
- 「やりたいこと」のねつ造: 面接で「やりたいこと」を問われた際に、表面的な志望動機や、その企業に合わせた建前を語ることが多くなります。
- 「できること」の限界: 専門性の乏しい学部・学科の場合、その企業は、採用してよい人材か判断がつきにくい場合が多くなります。
- ミスマッチの内定: 結果として、自身の価値観や適性と合わない企業から内定を得てしまうことが多くなります。
このような経緯で入社した学生は、入社後に「こんなはずじゃなかった」というギャップに直面します。
内定をもらえれば、どこでもいいという就活の結果です。
企業の文化や仕事内容が想像と異なり、自身の「仕事観」や「人生観」とかけ離れていることに気づくのです。
そして、「早期離職」「退職代行」の利用などへと繋がっていきます。
3. 専門学校の「スカウト型就活」との比較
一方で、専門学校の就職活動は、大学とは大きく異なります。
専門学校の「スカウト型就活」: 専門分野に特化した学校であるため、企業側が学校に直接求人を出す形式が一般的です。つまりスカウト型です。企業は、その専門分野を学んできた学生を求めており、学校側も学生の専門性やスキルを把握しているため、マッチングの精度が高くなります。
- スキルの明確化: 学生は入学前から、自分が何を学び、どのような職種に就きたいかという明確な目標を持っており、「資格取得」「技術の向上」に取り組んでいます。
- ミスマッチの少なさ: 企業と学生双方のニーズが最初から合致しているため、入社後のギャップが少なく、定着に繋がります。
この専門学校の就活スタイルは、高校時代に明確な「仕事観」や「人生観」を持って進路を選択した結果です。大学の「売り込み型就活」と比較すると、就職活動のミスマッチが、その前の「進路選択段階」から始まっていることに気づきます。
まとめ
「とりあえず大学」という進路選択は、高校時代の「仕事観」や「人生観」の“無意識”から始まる「ボタンの掛け違い」です。
「高校時代にそこまで真剣に考えていなかった」という保護者も多いはずですが、今は、そういう時代です。
このズレは、大学でのミスマッチを経て、就職活動における「売り込み型」の困難さに直面し、結果として就職ミスマッチや早期離職、さらには退職代行の増加という社会問題へと繋がっています。
本当に望ましいキャリアを築くためには、高校生はもちろん、高校の進路指導、保護者の求める「とりあえず大学」ではなく、本人の「仕事観」や「人生観」を深く見つめ直すことが大切です。
特に保護者の方は“ご自身の希望”ではなく“子どもの特性・資質”を十分に考慮してほしいと思います。
それが、その後の“学生生活”を充実させ、就職活動をより主体的なものに変え、最終的にミスマッチの少ないキャリアを歩むための第一歩となるのではないでしょうか。
大学に行くことだけが、進路の正解じゃありません。「何を学ぶか」「どう働きたいか」から考えると、『とりあえず』ではなく『本気で』学ぶ意味も見えてきて、専門学校のほうが合う人もたくさんいます。どんな分野があるのか見てからでも遅くありません。
あなたに合った専門学校がみつかるかもしれません。
| 専門学校は都道府県の認可校です |

読者対象
最新情報
- 社会人から美容師になるには
- 社会人から臨床工学技士になるには
- 社会人から理学療法士になるには
- 大学中退から保育士になるには
- 子供が大学を辞めることになる前に
- 「ありがとう」が聞こえる仕事へ。専門学校という選択
- 大学行きたくない 親に言えない
- 社会人から保育士になるには
- 「売り手市場」でも、やりたい仕事に就けるとは限らない!?
- 知らない人が結構多い!?専門学校AO入学エントリーに関する誤解
- 高校生の進路「早期内定」には要注意_複数校を比較して決めよう
- 「大学やめたい」「大学ついていけない」人がホントに多いんです
- 専門学校はメンタルとモチベ-ションを支える伴走型の環境です
- 大学受験につまずいても専門学校という選択肢、大学編入制度も
- 大学卒業後に専門学校を卒業した人_最終学歴は【大学卒】です
- 「進路 親のいいなり」―あなたの人生の”主役”は誰ですか?
- 大学中退から専門学校|卒業時は「新卒採用+スカウト型」就活
- 知らないと損 ハローワーク経由で “安く”保育士資格を取る制度
- 社会人から保育士に!専門学校で学ぶメリットと支援制度
- 内閣支持率「若者の価値観の変化」そこから見える進路のカタチ
- Fラン大・事実上無試験大の学生は企業からどう見られている?
- 経営悪化の私立大学に文科省が指導強化―価値のある進学とは?
- 親が進路を考えてくれない_どういう事?どうしたらいい?
- 専門学校は本当に楽しい?前向きの理由は在校生が感じる充実感
- 通信制専門学校_自分時間と両立し「資格・スキルを身につける」
- 大学の年内学力入試で進む、新たな「大学ミスマッチ」!?
- 行く価値のある専門学校とは?分野選びの指針と考え方
- 大学中退 親の気持ち
- 年内学力入試の導入で、「Fラン vs 専門学校」はもう古い考え方
- 年内学力入試が増えると、Fラン大学が見えにくくなる!?
- 専門学校に偏差値はある?知っておきたい入試の仕組み
- 大学年内入試拡大で専門学校の価値が上昇するこれだけの理由
- 「学びたい学生を迎えたい専門学校」と「人を集めたい大学」の違い
- AI時代に「とりあえず大学」「どこかに就職」の感覚じゃダメ
- ホテルで働きたい_方法はいくつかあります
- 社会人から専門学校へ_不安要素を解決!完全ガイド&学校紹介
- 大学を中退して専門学校へ_新たなスタートが生む自信と未来
- 大学中退後の3つの道:今すぐ中途採用・新卒正社員・公務員も
- 大学の年内学力入試が進む一方で──注目したい専門学校の実力
- AIで仕事はどうなる?高校生のための進路とキャリアガイド
- オールドメディアが報じない「専門学校」の実力こそ本当はスゴイ
- 大学中退 人生終了 今は辛い気持ちでも、必ず立ち直れます
- 子どもが大学を辞めたいと言ったら_専門学校で2年後正社員に
- リハビリの仕事に就くには:理学療法士と作業療法士の違いと、キャリアの選び方
- 「公務員になってほしい」保護者へ_各省庁に強い語学専門学校
- 理学療法と作業療法は何が違う?_やりたいリハビリはどっち?
- 大学中退は終わりじゃない。2年で「企業が欲しがる人材」になる
- ホテル専門学校に行く意味ある?―意味もあれば価値もあります
- ホテル専門学校って厳しい?ホテル業界はこんなに変化している
- 医療現場をテクノロジーで支える仕事— 臨床工学技士とは?
- 保育士を目指す大学と専門学校の違い、どっちがおすすめ?
- 映像クリエイターを目指す専門学校_きっと観てる“実写”映像
- AI時代のIT業界の目指し方_大学? 専門学校? 選び方完全ガイド
- 特色ある学科・学び方の専門学校
- 指定校推薦で大学中退した子どもへ – 親ができるサポートとは
- 「なんとなく大学」合わずに中退_仕事観で出会えた専門学校
- 高校生の子供が進路を迷っている、親はどう対応すればいい?
- 「就職ミスマッチ」は避けられる!? 専門学校=業界付属校の強み
- 大学中退から専門学校「再スタート迷子」にならない進路の選び方
- Fラン大と専門学校どっちがいい? そもそも「次元が違う」話
- 高校卒業してからじゃ遅いんです_就活迷子にならない進路選び
- 専門学校の就活は「スカウト型」_大学の就活は「売り込み型」
- 専門学校のいいところが今の高校生に合っている7つの理由
- 大学中退は親泣かせ?親の気持ち_心配は当然・次どうするの?
- 高校1・2年生の進路選び、親子でチェック指定校推薦の”注意点”
- Fラン中退する人、専門学校で伸びる人、子どもに合う進路とは?
- 指定校推薦の退学者が増加中_高校と大学の”取引”に生徒は不在
- Z世代の再起動=親世代に定着した「常識」の上書きが始まった
- 氷河期世代の子供(Z世代)の君へ 「自分らしい」進路の見つけ方
- 指定校推薦デメリット_大学進学前に親子で確認したいこと
- 専門学校へ行こうよ
- 未経験でもゴールが見える専門学校_行くメリット
- 「いい大学じゃないと、いい会社には入れない」は本当?実はね!
- 大学ミスマッチの先に見え隠れする就職ミスマッチ・退職代行
- 高校卒業後どうする?どうしたい?で、悩んでいるあなたへ
- Fラン大に進学したら「まわりが驚くほどやる気がない」は本当?
- 指定校推薦で、「うまくいった人」「失敗した人」に学ぶヒント
- 高校2年で進路が決まっていないけど、何か問題ありますか?
- 「専門学校意味ない」は間違い──そう言えるのは実力のある人
- 評価は学歴から学習歴へ_人材採用が“進化”「令和の真価論」