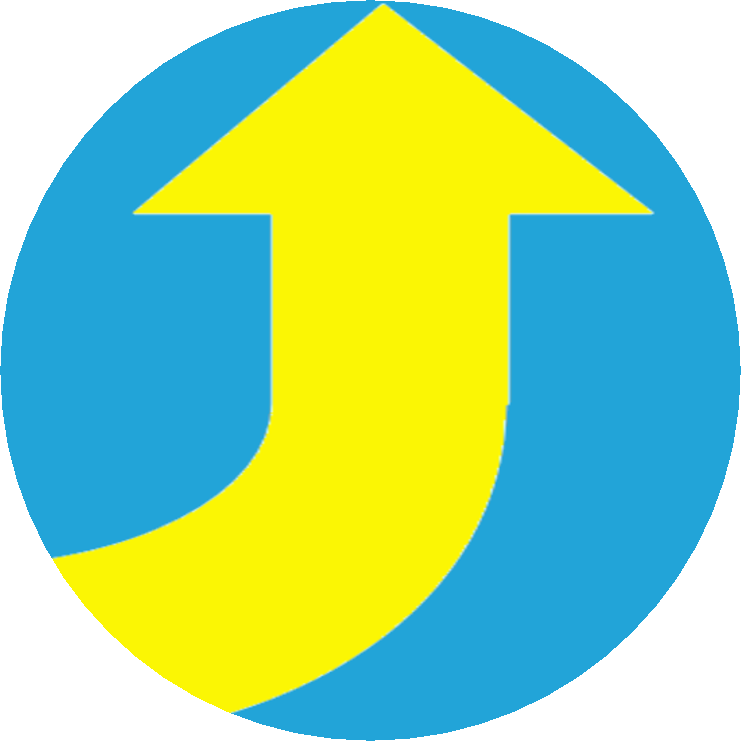落ちない安心の先に、落とし穴もある
指定校推薦――
「ほぼ合格確実」「早く決まる」「学力勝負じゃない」
高校生にも保護者にも人気の進路ルートです
でも実は、“ラクして進学”の裏に後悔が生まれやすい選択肢でもあります
指定校推薦には、デメリットもあるということを認識してください
対象の大学・学部に興味がありますか?
そもそも、「その大学」「その学部」をどれだけ知っていますでしょうか?
「指定校推薦」という、“魅力的な言葉”だけで決めることは要注意です
デメリットもあるということを
しっかり知っておくだけで、「こんなはずじゃなかった」を減らせます
1. いったん出願したら、辞退できない
デメリット:進路の選び直しがきかない
指定校推薦は「出願=進学確約」
合格したら、その大学に必ず入学しなければいけません
つまり、あとから迷っても後戻りできないのです
➤ どうなる?
・「別の大学を見つけても、もう手遅れ」
・「やりたいことが変わっても進路変更できない」
・進学してから「なんか違った…」と後悔する人も少なくありません
2. 入学後に「ついていけない」と感じる人も
デメリット:学力・意欲のギャップが大きいことも
指定校推薦は、一般入試よりも学力的なハードルが低いです
一方で、同じ学部には一般受験で必死に入ってきた学生もいます
つまり、必然的に学力の差が生じます
➤ どうなる?
・授業についていけない
・周囲との差に自信を失う
・「なんでこの大学に来たんだっけ?」とモヤモヤする
特に偏差値が高くない高校出身者は、学力差が顕著に出やすいという声もあります
3. 周囲から「楽して入った人」と見られることがある
デメリット:自分の評価が下がることも
大学によっては、指定校推薦組が
「ラクして入った」「勉強しない」
というレッテルを貼られることがあります
もちろん、推薦を取るためにコツコツ努力してきた人もたくさんいます
でも、入学後の印象はまた別の話です
➤ どうなる?
・ゼミや授業で「ラクして入った人」扱いされる
・人間関係で引け目を感じる
・せっかくの大学生活が居心地悪くなる
入学方法ってバレるの?
結論から言うと、バレる可能性はあります
なぜ、バレるかというと
1)入試区分で名簿管理されている
大学側は、入学時に「一般入試」「推薦入試(指定校・公募)」「AO」などの区分で合否管理をしています
その情報は教員や一部の職員には共有されていることもあります
2)授業やテストで“浮く”こともある
一般受験組が受験で勉強した内容に対して、授業に「ついていけない」となると、
「あ、この人は推薦組かな?」と学力面から推測されてしまうケースも
3)出身高校名から推察されるケース
同級生の間で情報が出回ることもあります
4. 親子ともに「早く決まる安心感」に流される
デメリット:進路の目的があいまいなまま決定してしまう
保護者としても、早く決まるのは安心材料です。
でもその安心が、「本当にやりたいこと」を考える機会を奪うことも
➤ どうなる?
・本人はモヤモヤしたまま進学
・大学生活がうまくいかず、途中で中退するケースも
・進学=ゴールだと思っていたが、その後が続かない
5. 指定校推薦は“楽な道”じゃない。選ぶのは「覚悟」
指定校推薦は、合格しやすい
でもそれは、進路の責任をすべて自分で背負うということでもあります
「行けると言われたから行く」のではなく、「行きたいから選ぶ」――
この意識がないと、入学後に苦しくなる場面が出てきます
「入りやすい大学=進級しやすい大学」ではありません
最後に|親子で話したい、たった一つの問いかけ
この進路は、今の自分にとって(お子様にとって)
「一番ラク」な道?
それとも「一番納得できる」道?
早く決まる進路より、納得して進む進路を選んでください
指定校推薦が悪いのではありません
でも、それが、「本当に自分が望んでいる進学かどうか」は、
ちゃんと考えて選びたいですね
大学に行くことだけが、進路の正解じゃありません。「何を学ぶか」「どう働きたいか」から考えると、『とりあえず』ではなく『本気で』学ぶ意味も見えてきて、専門学校のほうが合う人もたくさんいます。どんな分野があるのか見てからでも遅くありません。
あなたに合った専門学校がみつかるかもしれません。
| 専門学校は都道府県の認可校です |

読者対象
最新情報
- 子供が大学を辞めることになる前に
- 「ありがとう」が聞こえる仕事へ。専門学校という選択
- 大学行きたくない 親に言えない
- 社会人から保育士になるには
- 「売り手市場」でも、やりたい仕事に就けるとは限らない!?
- 知らない人が結構多い!?専門学校AO入学エントリーに関する誤解
- 高校生の進路「早期内定」には要注意_複数校を比較して決めよう
- 「大学やめたい」「大学ついていけない」人がホントに多いんです
- 専門学校はメンタルとモチベ-ションを支える伴走型の環境です
- 大学受験につまずいても専門学校という選択肢、大学編入制度も
- 大学卒業後に専門学校を卒業した人_最終学歴は【大学卒】です
- 「進路 親のいいなり」―あなたの人生の”主役”は誰ですか?
- 大学中退から専門学校|卒業時は「新卒採用+スカウト型」就活
- 知らないと損 ハローワーク経由で “安く”保育士資格を取る制度
- 社会人から保育士に!専門学校で学ぶメリットと支援制度
- 内閣支持率「若者の価値観の変化」そこから見える進路のカタチ
- Fラン大・事実上無試験大の学生は企業からどう見られている?
- 経営悪化の私立大学に文科省が指導強化―価値のある進学とは?
- 親が進路を考えてくれない_どういう事?どうしたらいい?
- 専門学校は本当に楽しい?前向きの理由は在校生が感じる充実感
- 通信制専門学校_自分時間と両立し「資格・スキルを身につける」
- 大学の年内学力入試で進む、新たな「大学ミスマッチ」!?
- 行く価値のある専門学校とは?分野選びの指針と考え方
- 大学中退 親の気持ち
- 年内学力入試の導入で、「Fラン vs 専門学校」はもう古い考え方
- 年内学力入試が増えると、Fラン大学が見えにくくなる!?
- 専門学校に偏差値はある?知っておきたい入試の仕組み
- 大学年内入試拡大で専門学校の価値が上昇するこれだけの理由
- 「学びたい学生を迎えたい専門学校」と「人を集めたい大学」の違い
- AI時代に「とりあえず大学」「どこかに就職」の感覚じゃダメ
- ホテルで働きたい_方法はいくつかあります
- 社会人から専門学校へ_不安要素を解決!完全ガイド&学校紹介
- 大学を中退して専門学校へ_新たなスタートが生む自信と未来
- 大学中退後の3つの道:今すぐ中途採用・新卒正社員・公務員も
- 大学の年内学力入試が進む一方で──注目したい専門学校の実力
- AIで仕事はどうなる?高校生のための進路とキャリアガイド
- オールドメディアが報じない「専門学校」の実力こそ本当はスゴイ
- 大学中退 人生終了 今は辛い気持ちでも、必ず立ち直れます
- 子どもが大学を辞めたいと言ったら_専門学校で2年後正社員に
- リハビリの仕事に就くには:理学療法士と作業療法士の違いと、キャリアの選び方
- 「公務員になってほしい」保護者へ_各省庁に強い語学専門学校
- 理学療法と作業療法は何が違う?_やりたいリハビリはどっち?
- 大学中退は終わりじゃない。2年で「企業が欲しがる人材」になる
- ホテル専門学校に行く意味ある?―意味もあれば価値もあります
- ホテル専門学校って厳しい?ホテル業界はこんなに変化している
- 医療現場をテクノロジーで支える仕事— 臨床工学技士とは?
- 保育士を目指す大学と専門学校の違い、どっちがおすすめ?
- 映像クリエイターを目指す専門学校_きっと観てる“実写”映像
- AI時代のIT業界の目指し方_大学? 専門学校? 選び方完全ガイド
- 特色ある学科・学び方の専門学校
- 指定校推薦で大学中退した子どもへ – 親ができるサポートとは
- 「なんとなく大学」合わずに中退_仕事観で出会えた専門学校
- 高校生の子供が進路を迷っている、親はどう対応すればいい?
- 「就職ミスマッチ」は避けられる!? 専門学校=業界付属校の強み
- 大学中退から専門学校「再スタート迷子」にならない進路の選び方
- Fラン大と専門学校どっちがいい? そもそも「次元が違う」話
- 高校卒業してからじゃ遅いんです_就活迷子にならない進路選び
- 専門学校の就活は「スカウト型」_大学の就活は「売り込み型」
- 専門学校のいいところが今の高校生に合っている7つの理由
- 大学中退は親泣かせ?親の気持ち_心配は当然・次どうするの?
- 高校1・2年生の進路選び、親子でチェック指定校推薦の”注意点”
- Fラン中退する人、専門学校で伸びる人、子どもに合う進路とは?
- 指定校推薦の退学者が増加中_高校と大学の”取引”に生徒は不在
- Z世代の再起動=親世代に定着した「常識」の上書きが始まった
- 氷河期世代の子供(Z世代)の君へ 「自分らしい」進路の見つけ方
- 指定校推薦デメリット_大学進学前に親子で確認したいこと
- 専門学校へ行こうよ
- 未経験でもゴールが見える専門学校_行くメリット
- 「いい大学じゃないと、いい会社には入れない」は本当?実はね!
- 大学ミスマッチの先に見え隠れする就職ミスマッチ・退職代行
- 高校卒業後どうする?どうしたい?で、悩んでいるあなたへ
- Fラン大に進学したら「まわりが驚くほどやる気がない」は本当?
- 指定校推薦で、「うまくいった人」「失敗した人」に学ぶヒント
- 高校2年で進路が決まっていないけど、何か問題ありますか?
- 「専門学校意味ない」は間違い──そう言えるのは実力のある人
- 評価は学歴から学習歴へ_人材採用が“進化”「令和の真価論」
- 大学のオープンキャンパスで見た、親子のリアルなすれ違い
- 親に進路を反対されたらどうする?
- 学部が決められないのに大学進学?─進路の矛盾に気が付いた
- 学歴にこだわる親をどう説得する?親の理解と子供の進路戦略