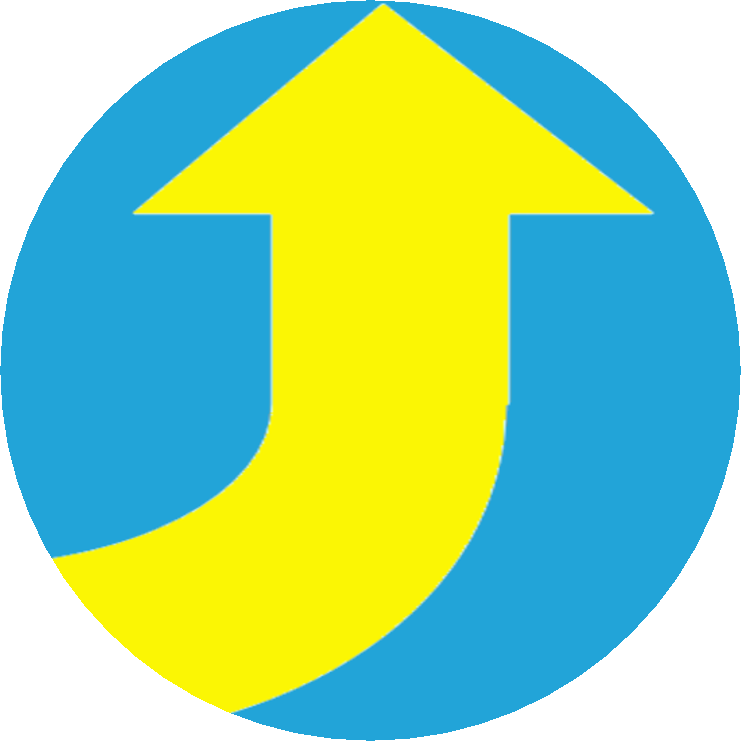第1章:指定校推薦が「枠」で決まる、まるで進路ガチャ
成績がふるわない生徒にも、大学から「指定校推薦」の枠が提示される
しかも、それを勧めてくるのは、高校の先生自身であることはご承知のとおり
特に、偏差値の高くない高校ではこの傾向が強く、「大学に行けるならありがたい」と思わせる構図ができあがっています
そもそも、指定校推薦とは、大学が「この高校から生徒を受け入れたい」と枠を提示する制度
でも現場では、“進学実績を作りたい高校”と、“定員を埋めたい大学”の利害が一致した取引のようになっていることも──。
これでは、本来の目的である「生徒の希望や適性に合った進学」とはかけ離れています
第2章:「うちの子が大学に行けるなら…」の構図
高校で行われる三者面談
ここで指定校推薦の話をされると、多くの保護者はこう思います
「うちの子が大学に行けるなら、ありがたいです」
でも、その提案は生徒の本音や将来像を十分に聞いた上でのものではないことも多いのです
「とにかく大学に進学」という進路指導が、知らず知らずのうちに当たり前になっていませんか?
親が強く押しているのではなく、「先生がそう言うなら」と受け入れてしまう
本当の希望や適性を置き去りにしたまま、進学が決まっていくケースが後を絶ちません
第3章:専門学校は最初から、意図的に“視界の外”に
専門学校の募集担当者が高校にあいさつ回りに行っても、「職員室に入れてもらえず廊下で立ち話」など、冷たい対応を受けることがあるといいます
ひどい場合は、職員室の奥で先生が両手でバツ印を出して「居留守」の合図をしている場面すら──。
つまり、多くの高校では、最初から専門学校という選択肢を“見せようとしない”のです
教員が専門学校に対する理解を深めようという姿勢がなければ、生徒に伝わることもありません
選択肢が示されなければ、生徒は「知らなかったから選べなかった」まま、進路を決めるしかなくなります
第4章:進路ガイダンスは“外注”まかせ
高校で開かれる進路ガイダンスは、多くの場合、外部の会社が運営しています
この会社が大学や専門学校に声をかけて集め、学校説明の場をつくっています
問題は、専門学校は参加費を払って出展するのに、ネームバリューのある大学は無料で参加できること、さらに専門学校はメインではない扱いという点です
そのため、ガイダンスの会場では「大学ばかりが目立ち、専門学校は少数派」という構図になりがちです
さらに、偏差値の低い大学(いわゆるFランク大学)は、高校からも外部会社からも声がかからず、参加できないこともあります
そんな大学でも「指定校推薦枠」という切り札を持っており、偏差値の高くない高校に対して、入学受け入れの提示を行っています
ガイダンスの現場では、結果として、生徒が接する進路情報は、最初から偏った内容になっているのです
ガイダンスで「どんな学校に出会えるか」は、生徒の努力とは関係のないところで決まっている
そんな現実を、保護者も知っておく必要があります
第5章:あの進路指導は誰のためか
「指定校推薦で進学したものの、大学を辞めてしまう生徒が増えている」──
こうしたニュースの背景には、こうした進路指導のあり方があります
とくに、偏差値の低い高校から進学した生徒に退学が目立つというデータも
成績や興味に合わない大学へ、強引に進学してしまった結果とも言えるでしょう
進路指導は本来、「生徒の人生を支える道しるべ」であるべきです
にもかかわらず、大学の都合、高校の実績づくり、の流れに流されていないでしょうか
保護者の方、高校生のみなさん、進路を選ぶときは、「自分の未来に納得できる選択か?」という視点を、思い出してください
おわりに:その進路、本当に「自分の意思」ですか?
指定校推薦という制度は、うまく活用すれば、生徒にとって負担の少ない進学方法です
けれど、現場ではその“便利さ”に頼りすぎて、本来向き合うべき「本人の希望や適性」が置き去りにされているケースが増えています
高校の進路指導、大学の募集枠、外部委託のガイダンスの構造──
すべてが「本人の意思決定」を後回しにするような仕組みになっていないでしょうか
「うちの子が大学に行けるなら…」という親の安心感も、
「なんとなく推薦があるから…」という高校生の曖昧な気持ちも、
気づけば、誰かの手によって決められたレールに乗っている状態、
「選んでいるつもりが、実は、選ばされている進学」になっていませんか?
進路選びは、ゴールではなく、スタートです
今の選択が、将来の可能性を開くものになるように──
「自分の意思で選ぶ」ことを、どうか忘れないでください
大学に行くことだけが、進路の正解じゃありません。「何を学ぶか」「どう働きたいか」から考えると、『とりあえず』ではなく『本気で』学ぶ意味も見えてきて、専門学校のほうが合う人もたくさんいます。どんな分野があるのか見てからでも遅くありません。
あなたに合った専門学校がみつかるかもしれません。
| 専門学校は都道府県の認可校です |

読者対象
最新情報
- 子供が大学を辞めることになる前に
- 「ありがとう」が聞こえる仕事へ。専門学校という選択
- 大学行きたくない 親に言えない
- 社会人から保育士になるには
- 「売り手市場」でも、やりたい仕事に就けるとは限らない!?
- 知らない人が結構多い!?専門学校AO入学エントリーに関する誤解
- 高校生の進路「早期内定」には要注意_複数校を比較して決めよう
- 「大学やめたい」「大学ついていけない」人がホントに多いんです
- 専門学校はメンタルとモチベ-ションを支える伴走型の環境です
- 大学受験につまずいても専門学校という選択肢、大学編入制度も
- 大学卒業後に専門学校を卒業した人_最終学歴は【大学卒】です
- 「進路 親のいいなり」―あなたの人生の”主役”は誰ですか?
- 大学中退から専門学校|卒業時は「新卒採用+スカウト型」就活
- 知らないと損 ハローワーク経由で “安く”保育士資格を取る制度
- 社会人から保育士に!専門学校で学ぶメリットと支援制度
- 内閣支持率「若者の価値観の変化」そこから見える進路のカタチ
- Fラン大・事実上無試験大の学生は企業からどう見られている?
- 経営悪化の私立大学に文科省が指導強化―価値のある進学とは?
- 親が進路を考えてくれない_どういう事?どうしたらいい?
- 専門学校は本当に楽しい?前向きの理由は在校生が感じる充実感
- 通信制専門学校_自分時間と両立し「資格・スキルを身につける」
- 大学の年内学力入試で進む、新たな「大学ミスマッチ」!?
- 行く価値のある専門学校とは?分野選びの指針と考え方
- 大学中退 親の気持ち
- 年内学力入試の導入で、「Fラン vs 専門学校」はもう古い考え方
- 年内学力入試が増えると、Fラン大学が見えにくくなる!?
- 専門学校に偏差値はある?知っておきたい入試の仕組み
- 大学年内入試拡大で専門学校の価値が上昇するこれだけの理由
- 「学びたい学生を迎えたい専門学校」と「人を集めたい大学」の違い
- AI時代に「とりあえず大学」「どこかに就職」の感覚じゃダメ
- ホテルで働きたい_方法はいくつかあります
- 社会人から専門学校へ_不安要素を解決!完全ガイド&学校紹介
- 大学を中退して専門学校へ_新たなスタートが生む自信と未来
- 大学中退後の3つの道:今すぐ中途採用・新卒正社員・公務員も
- 大学の年内学力入試が進む一方で──注目したい専門学校の実力
- AIで仕事はどうなる?高校生のための進路とキャリアガイド
- オールドメディアが報じない「専門学校」の実力こそ本当はスゴイ
- 大学中退 人生終了 今は辛い気持ちでも、必ず立ち直れます
- 子どもが大学を辞めたいと言ったら_専門学校で2年後正社員に
- リハビリの仕事に就くには:理学療法士と作業療法士の違いと、キャリアの選び方
- 「公務員になってほしい」保護者へ_各省庁に強い語学専門学校
- 理学療法と作業療法は何が違う?_やりたいリハビリはどっち?
- 大学中退は終わりじゃない。2年で「企業が欲しがる人材」になる
- ホテル専門学校に行く意味ある?―意味もあれば価値もあります
- ホテル専門学校って厳しい?ホテル業界はこんなに変化している
- 医療現場をテクノロジーで支える仕事— 臨床工学技士とは?
- 保育士を目指す大学と専門学校の違い、どっちがおすすめ?
- 映像クリエイターを目指す専門学校_きっと観てる“実写”映像
- AI時代のIT業界の目指し方_大学? 専門学校? 選び方完全ガイド
- 特色ある学科・学び方の専門学校
- 指定校推薦で大学中退した子どもへ – 親ができるサポートとは
- 「なんとなく大学」合わずに中退_仕事観で出会えた専門学校
- 高校生の子供が進路を迷っている、親はどう対応すればいい?
- 「就職ミスマッチ」は避けられる!? 専門学校=業界付属校の強み
- 大学中退から専門学校「再スタート迷子」にならない進路の選び方
- Fラン大と専門学校どっちがいい? そもそも「次元が違う」話
- 高校卒業してからじゃ遅いんです_就活迷子にならない進路選び
- 専門学校の就活は「スカウト型」_大学の就活は「売り込み型」
- 専門学校のいいところが今の高校生に合っている7つの理由
- 大学中退は親泣かせ?親の気持ち_心配は当然・次どうするの?
- 高校1・2年生の進路選び、親子でチェック指定校推薦の”注意点”
- Fラン中退する人、専門学校で伸びる人、子どもに合う進路とは?
- 指定校推薦の退学者が増加中_高校と大学の”取引”に生徒は不在
- Z世代の再起動=親世代に定着した「常識」の上書きが始まった
- 氷河期世代の子供(Z世代)の君へ 「自分らしい」進路の見つけ方
- 指定校推薦デメリット_大学進学前に親子で確認したいこと
- 専門学校へ行こうよ
- 未経験でもゴールが見える専門学校_行くメリット
- 「いい大学じゃないと、いい会社には入れない」は本当?実はね!
- 大学ミスマッチの先に見え隠れする就職ミスマッチ・退職代行
- 高校卒業後どうする?どうしたい?で、悩んでいるあなたへ
- Fラン大に進学したら「まわりが驚くほどやる気がない」は本当?
- 指定校推薦で、「うまくいった人」「失敗した人」に学ぶヒント
- 高校2年で進路が決まっていないけど、何か問題ありますか?
- 「専門学校意味ない」は間違い──そう言えるのは実力のある人
- 評価は学歴から学習歴へ_人材採用が“進化”「令和の真価論」
- 大学のオープンキャンパスで見た、親子のリアルなすれ違い
- 親に進路を反対されたらどうする?
- 学部が決められないのに大学進学?─進路の矛盾に気が付いた
- 学歴にこだわる親をどう説得する?親の理解と子供の進路戦略