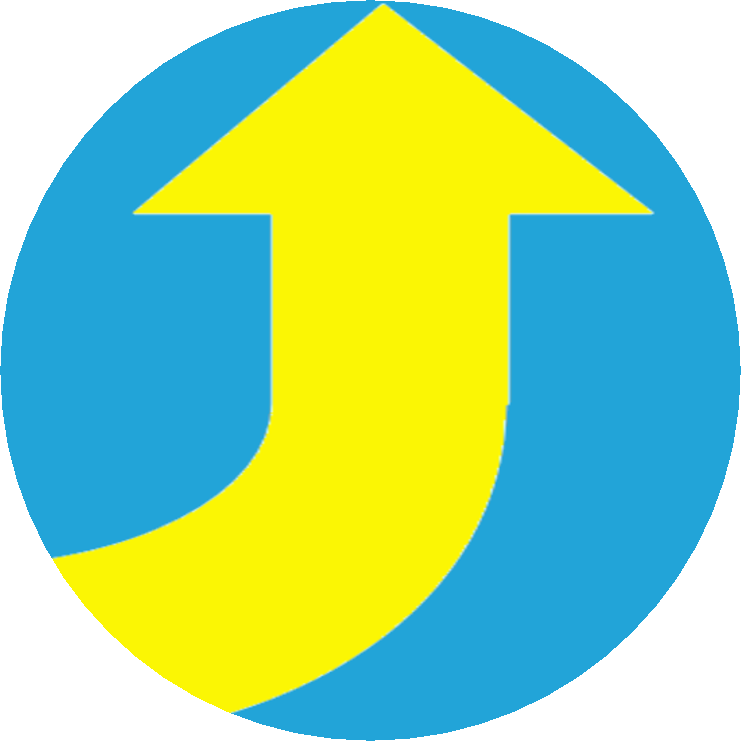はじめに
大学は増えすぎ定員割れが当たり前
学力や適性に合わない“とりあえず大学”が広がり、入学後のミスマッチが深刻化
けれど今、
ようやく一部の高校生や保護者がその危うさに気づき始めました
これは、大学進学の“一部の慣れてしまった常識”を問い直す転機かもしれません
■ Fラン大学、なぜこんなに増えたのか
私立大学は全国に600校以上、じつにその約6割が定員割れの状態です
少子化で18歳人口が減っているのに新設や拡張は止まらない
30年も前から指摘されてきましたが結局、見直されませんでした
その背景にあるのが、
“大学設立=ビジネス”としての視点
大学設置の認可は、文科省が行いますが、
「天下り先」「利権構造」「地域振興の名目」など、教育とは異なる問題が指摘されてきたのは事実です
大学の新設は相次ぎ、
その中には学力向上や教育理念に疑問符が付くような大学も少なくありません
学生のためというより、
「教育の名を借りた“箱もの”」として大学が量産されてきたのです
■ 指定校推薦が支える“空虚な大学”の実態
Fラン大学にとって、安定した学生確保の手段が「指定校推薦」です
事実上、学力試験なしで高校から学生を受け入れる仕組みは、
本来、意欲や適性を重視するもののはずでした
しかし現実には、偏差値の低い高校にも推薦枠を広げる動きが広がり、
高校側も大学実績を上げるために、大学ありきの指導を進めています
こうして進学した学生の多くが、入学後に
「講義についていけない」「学ぶ目的が見つからない」とつまずき、
退学・休学の増加につながっているのです
■ 「学費支援」が招く“合わない進学”の連鎖
経済的に厳しい家庭の学生にも進学のチャンスを──。
そんな目的で導入されたのが「修学支援新制度」です
しかし、制度の恩恵を受けるために、「進学そのもの」が目的化され、
本人の学力や興味に関係なく大学を選ぶケースが増えました
「成績が悪くても」
「お金がなくても」
「ほぼ試験なしで」
進学できる仕組みは、
“誰でも大学に進学して卒業できる”という幻想を強めてしまったのです
そんな状況が、逆に“無理な大学進学”を後押ししている現実があります
支援制度は重要ですが、「進学前に立ち止まって考える」機会を失ってしまった側面は否定できません
■ 親はなぜ、進学ミスマッチを見抜けなかったのか
今の高校生の親世代(40〜50代)は、かつて「就職氷河期」を経験しています
当時、高校卒業後の就職が「狭き門」となり、「より良い就職先を得るために大学進学」という考え方が定着したのです
その意識は今も根付いています
だからこそ、子どもには「安定のために大学へ」と願う気持ちも理解できます
とはいえ、近年はオープンキャンパスにも親の同伴も多く、
進学先について情報を得る機会はむしろ増えています
それなのに、なぜ“進学の失敗”を防げなかったのか?
それは、
「指定校推薦だから大丈夫」
「大学へ行けば何とかなる」
という思い込みが強く、
「何を勉強するのか」
「子どもは続けられるか」という
最も基本的な部分が、抜け落ちてしまったからです
その結果、ミスマッチを見抜く目を曇らせてしまったのではないでしょうか
■ それでも、気づき始めた親と子
最近、ある変化が見られます
「進学ミスマッチ」「指定校推薦で退学者が急増」などのニュースを通じて大学の実態に触れた高校生・保護者が、今の進路指導に疑問を抱きはじめています
「本当にその大学に行く必要があるのか」
「大学だけが進路ではないのではないか」
「専門学校の情報が少な過ぎないか」
などを問い直し始めています
大学という肩書ではなく、
「自分に合った学び方・生き方」を選びたいという思いが、若い世代の中に、確実に芽生え始めています
■ 誰のための何のための進学か──問い直すとき
進学とは、「子どもが自分で選ぶ人生のスタート地点」のはずです
けれど今は、親や高校、大学側の都合で「選ばされた進学」があまりに多い
・定員を埋めたい大学
・実績をつくりたい高校
・将来が不安と感じる親
その三者の思惑が合致すると、子ども本人の意志や適性は置き去りになります
もう一度問い直すべきです─「誰のための進学か?」と
本当に子どもに必要なのは、
“とりあえず大学”ありません
納得のいく人生の選択肢を、一緒に考える姿勢です
高校や大学、そして親が押しつけた“進学ルート”に流されるのではなく
本人が、
「なぜそこに行きたいのか」
「何を学びたいのか」
を考える
「それを保護者と共有する」
それが、
進学のミスマッチを防ぐ唯一の方法です
大学に行くか、行かないかではなく
「納得して選べたかどうか」こそが大切な時代になっています
まとめ:ようやく始まった目覚めのきっかけ
Fラン大学の量産と大学神話の崩壊は、一部の高校生と保護者にとって、ようやく「目覚め」のきっかけになり始めました
■ 大学はゴールではない
■ 学費支援は手段であって目的ではない
■ 進学は「選ぶ」ものであり、「選ばされる」ものではない
この当たり前に、ようやく戻ろうとしています
さあ、素晴らしい時代の始まりです
大学に行くことだけが、進路の正解じゃありません。「何を学ぶか」「どう働きたいか」から考えると、『とりあえず』ではなく『本気で』学ぶ意味も見えてきて、専門学校のほうが合う人もたくさんいます。どんな分野があるのか見てからでも遅くありません。
あなたに合った専門学校がみつかるかもしれません。
| 専門学校は都道府県の認可校です |

読者対象
最新情報
- 子供が大学を辞めることになる前に
- 「ありがとう」が聞こえる仕事へ。専門学校という選択
- 大学行きたくない 親に言えない
- 社会人から保育士になるには
- 「売り手市場」でも、やりたい仕事に就けるとは限らない!?
- 知らない人が結構多い!?専門学校AO入学エントリーに関する誤解
- 高校生の進路「早期内定」には要注意_複数校を比較して決めよう
- 「大学やめたい」「大学ついていけない」人がホントに多いんです
- 専門学校はメンタルとモチベ-ションを支える伴走型の環境です
- 大学受験につまずいても専門学校という選択肢、大学編入制度も
- 大学卒業後に専門学校を卒業した人_最終学歴は【大学卒】です
- 「進路 親のいいなり」―あなたの人生の”主役”は誰ですか?
- 大学中退から専門学校|卒業時は「新卒採用+スカウト型」就活
- 知らないと損 ハローワーク経由で “安く”保育士資格を取る制度
- 社会人から保育士に!専門学校で学ぶメリットと支援制度
- 内閣支持率「若者の価値観の変化」そこから見える進路のカタチ
- Fラン大・事実上無試験大の学生は企業からどう見られている?
- 経営悪化の私立大学に文科省が指導強化―価値のある進学とは?
- 親が進路を考えてくれない_どういう事?どうしたらいい?
- 専門学校は本当に楽しい?前向きの理由は在校生が感じる充実感
- 通信制専門学校_自分時間と両立し「資格・スキルを身につける」
- 大学の年内学力入試で進む、新たな「大学ミスマッチ」!?
- 行く価値のある専門学校とは?分野選びの指針と考え方
- 大学中退 親の気持ち
- 年内学力入試の導入で、「Fラン vs 専門学校」はもう古い考え方
- 年内学力入試が増えると、Fラン大学が見えにくくなる!?
- 専門学校に偏差値はある?知っておきたい入試の仕組み
- 大学年内入試拡大で専門学校の価値が上昇するこれだけの理由
- 「学びたい学生を迎えたい専門学校」と「人を集めたい大学」の違い
- AI時代に「とりあえず大学」「どこかに就職」の感覚じゃダメ
- ホテルで働きたい_方法はいくつかあります
- 社会人から専門学校へ_不安要素を解決!完全ガイド&学校紹介
- 大学を中退して専門学校へ_新たなスタートが生む自信と未来
- 大学中退後の3つの道:今すぐ中途採用・新卒正社員・公務員も
- 大学の年内学力入試が進む一方で──注目したい専門学校の実力
- AIで仕事はどうなる?高校生のための進路とキャリアガイド
- オールドメディアが報じない「専門学校」の実力こそ本当はスゴイ
- 大学中退 人生終了 今は辛い気持ちでも、必ず立ち直れます
- 子どもが大学を辞めたいと言ったら_専門学校で2年後正社員に
- リハビリの仕事に就くには:理学療法士と作業療法士の違いと、キャリアの選び方
- 「公務員になってほしい」保護者へ_各省庁に強い語学専門学校
- 理学療法と作業療法は何が違う?_やりたいリハビリはどっち?
- 大学中退は終わりじゃない。2年で「企業が欲しがる人材」になる
- ホテル専門学校に行く意味ある?―意味もあれば価値もあります
- ホテル専門学校って厳しい?ホテル業界はこんなに変化している
- 医療現場をテクノロジーで支える仕事— 臨床工学技士とは?
- 保育士を目指す大学と専門学校の違い、どっちがおすすめ?
- 映像クリエイターを目指す専門学校_きっと観てる“実写”映像
- AI時代のIT業界の目指し方_大学? 専門学校? 選び方完全ガイド
- 特色ある学科・学び方の専門学校
- 指定校推薦で大学中退した子どもへ – 親ができるサポートとは
- 「なんとなく大学」合わずに中退_仕事観で出会えた専門学校
- 高校生の子供が進路を迷っている、親はどう対応すればいい?
- 「就職ミスマッチ」は避けられる!? 専門学校=業界付属校の強み
- 大学中退から専門学校「再スタート迷子」にならない進路の選び方
- Fラン大と専門学校どっちがいい? そもそも「次元が違う」話
- 高校卒業してからじゃ遅いんです_就活迷子にならない進路選び
- 専門学校の就活は「スカウト型」_大学の就活は「売り込み型」
- 専門学校のいいところが今の高校生に合っている7つの理由
- 大学中退は親泣かせ?親の気持ち_心配は当然・次どうするの?
- 高校1・2年生の進路選び、親子でチェック指定校推薦の”注意点”
- Fラン中退する人、専門学校で伸びる人、子どもに合う進路とは?
- 指定校推薦の退学者が増加中_高校と大学の”取引”に生徒は不在
- Z世代の再起動=親世代に定着した「常識」の上書きが始まった
- 氷河期世代の子供(Z世代)の君へ 「自分らしい」進路の見つけ方
- 指定校推薦デメリット_大学進学前に親子で確認したいこと
- 専門学校へ行こうよ
- 未経験でもゴールが見える専門学校_行くメリット
- 「いい大学じゃないと、いい会社には入れない」は本当?実はね!
- 大学ミスマッチの先に見え隠れする就職ミスマッチ・退職代行
- 高校卒業後どうする?どうしたい?で、悩んでいるあなたへ
- Fラン大に進学したら「まわりが驚くほどやる気がない」は本当?
- 指定校推薦で、「うまくいった人」「失敗した人」に学ぶヒント
- 高校2年で進路が決まっていないけど、何か問題ありますか?
- 「専門学校意味ない」は間違い──そう言えるのは実力のある人
- 評価は学歴から学習歴へ_人材採用が“進化”「令和の真価論」
- 大学のオープンキャンパスで見た、親子のリアルなすれ違い
- 親に進路を反対されたらどうする?
- 学部が決められないのに大学進学?─進路の矛盾に気が付いた
- 学歴にこだわる親をどう説得する?親の理解と子供の進路戦略