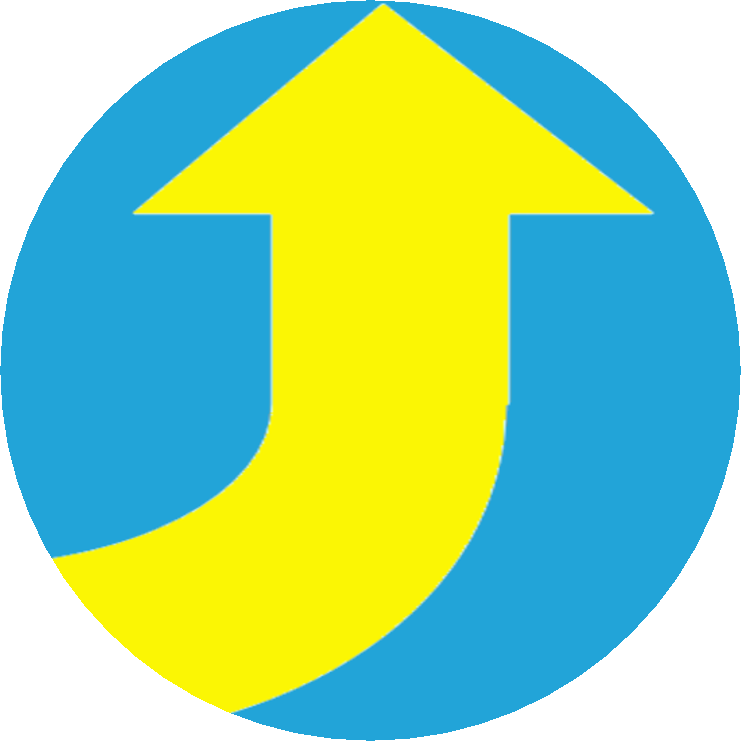就職氷河期──1993年~2005年頃に就職活動を行った世代は、バブル崩壊後の厳しい雇用環境に直面し、多くが非正規雇用や長期の就職活動を強いられました
2025年4月現在、おおむね40代から50代半ばくらいです
あれから20~30年以上、氷河期世代の多くが今、親となり、自分の子どもに進路の選択を迫られる場面に立っています
自身の苦い経験を乗り越えた今、子どもには何を伝えるべきなのか?
「いい大学に入れば安心」という時代が終わりつつある中で、親子の進路選びを見つめ直します

私たちは「就職氷河期世代」だった
バブル経済が崩壊し、後に「失われた30年」と呼ばれる時代に突入した1990年代。皆さんが社会に出たその頃、世の中には明るい未来よりも、不安と閉塞感が漂っていました
多くの企業が新卒採用を中止し、就職活動をしても内定が出ない。面接に進むことすら難しい。正社員の募集は極端に減り、非正規や契約社員といった「不安定な働き方」しか選択肢がない──そんな現実に、多くの同世代が直面しました
「就職氷河期世代」は、ちょうど今、40代〜50代半ばの年齢です
人生の中でも仕事や子育ての負荷が重なるこの時期に、改めて「あのとき何を選び、何を選べなかったか」と、自分の人生と向き合っているのかもしれません
“新卒で失敗すれば人生が終わる”という極端な価値観に苦しめられた世代。それでも、時には回り道をしながら、なんとかここまで歩んできたという実感がある方も多いのではないでしょうか
皆さんが歩んできた道は、決して順風満帆ではなかったかもしれません。しかし、だからこそ見えてくる「進路の意味」や「働くことの本質」もあるはずです
今、親という立場から子どもを見つめるとき、その経験がきっと活かせるのではないでしょうか

あの頃とは違う不安定さ分かりにくさ
皆さんが社会に出た90年代〜2000年代前半、日本は長く経済低迷の中にありました。終身雇用はすでに崩れ始めていたにもかかわらず、「安定を得るには正社員」「正社員になるには新卒で入社」という古い価値観だけが残っていたのです
一方で今の子どもたちが生きる社会は、表面的には「多様な働き方」や「個人の選択を尊重する時代」だとされています
しかし実態は、あの頃とはまた違った不安定さや分かりにくさが広がっています

社会と雇用「変化の年表」
規制緩和、構造改革など新自由主義的な政策の導入
終身雇用制度の変革、非正規雇用の拡大
| 年代 | 社会・政治の出来事 | 雇用の影響 |
| 1991年 | バブル崩壊 | 新卒採用大幅減、氷河期の始まり |
| 1999年 | 労働者派遣法改正 | 派遣労働の拡大、非正規が当たり前に |
| 2008年 | リーマンショック | 派遣切り、雇用不安再燃 |
| 2012年〜 | アベノミクス | 一部企業は回復も、格差固定化が進行 |
| 2020年~ | コロナ禍 | 業種によって雇用の明暗が分かれる |
このように、時代の節目ごとに雇用環境は大きく変化してきました。
しかし、その変化はいつも「働く個人」には厳しいものでした
日本社会の現実は「組織は個人を守らない」ということです
安定は「企業」ではなく「自分」で築く時代
かつては、「大企業に入れば一生安泰」と言われた時代が確かにありました。けれど今は、企業ですら未来の保証はできません。突然の業績不振でリストラされる、配置転換でまったく違う仕事を任される、副業や転職を前提としたキャリア設計が必要になる──そんな時代です
このような社会では、「安定」そのものの意味が変わっています。安定とは“安心して生きていける状態”のこと。けれどその方法は、一つではありません
職業の選び方、働き方、学び直しの仕方──すべてが自由である代わりに、自分で選び、自分で責任を持つ必要がある時代になったのです

あの頃から今まで「社会的影響が大きかった出来事」
※以下はほんの一部です
| 年代 | 社名・出来事 | 解説 |
| 1997年 | 山一證券が自主廃業 | 巨額の簿外債務が発覚し、経営が行き詰まる |
| 1998年 | 長銀(日本長期信用銀行)が経営破綻(国有化) | 不良債権問題深刻化 |
| 2002年 | そごうグループが経営破綻 | バブル期の積極的な投資が重荷に |
| 2004年 | カネボウが産業再生機構の支援決定 | 化粧品事業以外の不振が原因。後に花王が事業を買収 |
| 2006年 | ライブドア事件 | 粉飾決算や証券取引法違反で経営陣が逮捕される |
| 2011年 | オリンパス粉飾決算事件 | 巨額の損失隠しが発覚し、経営陣が逮捕される |
| 2015年 | 東芝の不正会計問題 | 長年にわたる不正会計が発覚し、2023年上場廃止に |
| 2017年 | タカタの経営破綻 | エアバッグ欠陥問題で巨額の負債を抱え、経営破綻 |
| 2020年~ | 新型コロナウイルス感染症拡大による業績不振とリストラ | 航空、観光、飲食業などを中心に多くの大企業が業績悪化に見舞われ、人員削減や早期退職を実施 |
| 2023年 | ビッグモーターによる保険金不正請求問題 | 自動車修理における保険金の不正請求が大規模に発覚 伊藤忠商事グループ「WECARS」などに分割継承 |
親の世代の「常識」は、もう通用しない
「とにかく大学に行って、大手に入れば安心」
「公務員になれば勝ち組」
「正社員なら何でもいい」
かつては信じられていたこのような“常識”は、すでに通用しなくなっています。子どもたちは今、「将来が見えない社会」の中で、自分の道を見つけなければならないのです。
だからこそ、皆さん親世代が自分の経験を“ただの成功・失敗談”として語るのではなく、「あの時代はこうだった」「今は違う」という視点で整理し、伝えていくことが大切になります。

高校の進路指導、親の時代とどう変わった?
皆さん親世代が高校生だった頃、進路指導はもっと“ばらけていた”印象がありませんか?
大学に進学する人もいれば、専門学校へ進む人、就職を選ぶ人などいろいろでした
インターネットもなく情報は進路指導室
インターネットのない時代、多くの情報は学校に集中していました
進路指導室にあった「大学のファイル」「専門学校のファイル」を覚えているでしょうか?
その後、インターネットの登場で「学校主導型」から「個人応募型」になりましたが、それでも高校の進路指導は、生徒の希望に沿って“ばらけていた”はずです
進路指導は個人尊重から大学偏重に
けれど、今の高校の進路指導では、「とりあえず大学へ行かせる」がほぼ当たり前です。少子化に加えて進学率の上昇と大学数の増加がその背景にありますが、それは本当に、子どもにとって“最善の選択肢”なのでしょうか?
大学進学率の上昇と「とりあえず大学」の空気
文部科学省のデータによると、1990年代初頭には40%台だった大学進学率が、今ではおよそ60%を超えています。大学そのものの数も増え、特に私立大学では“定員割れ”が常態化している学校も少なくありません
つまり、大学に入るハードルは昔より下がっている一方で、「大学に入ること」自体の価値も相対的に下がっているのです
さらに付け加えると「Fランク大学」「ボーダーフリー大学」のような入試が手続き化している「ほぼ誰でも入れる大学」では、退学率の高さも指摘されています
にもかかわらず、学校現場ではいまだに「大学進学=標準」「就職や専門学校=イレギュラー」という空気が根強く残っています

専門職や実務教育が軽視されている現実
親世代の中には、「手に職をつける」という表現に違和感を感じる人もいるかもしれません
この背景には「手に職より学歴」という偏った考え方が見え隠れします
事実、今の高校の進路指導では、専門学校や職業系の道について詳しく説明される機会は非常に限られています
「手に職」を今風に言い換えれば「資格取得」や「スキル・技術の習得」です
例えば、美容・保育・調理・建築・IT・ホテル・ファッションなど、社会に必要とされる実践的なスキルを学べる学校はたくさんあるのに、それらの情報が生徒や保護者に届く機会はたいへん少なく限定的なのが現状です

「とりあえず大学」から生まれるミスマッチ
子どもにとって進路選択は、人生の方向を左右する大きな決断です。けれど、「なんとなく大学へ進学したけど目的がない」「勉強についていけない」「辛い」「馴染めない」という声は、年々増えています
これは、本人だけの問題ではありません
大学偏重の進路指導や、親からの「とりあえず大学に行っておきなさい」という無意識のプレッシャーが、進路の“目的”を見失わせていることも少なくないのです
進路は「親が決める」ものではないけれど
進路は本来、子どもが自分で決めていくものです。ただし、その判断を支える情報や考え方は、親が“提供”できる部分でもあります
皆さん自身が「選べなかった」経験を持つ世代だからこそ、「何を選ぶか」だけでなく、「どう選ぶか」の大切さを伝えていく役割があるのかもしれません
子どもの進路とどう向き合うか──親としてできること
進路の話になると、つい「こうしたほうがいい」「それはやめておけ」と言いたくなってしまうのが親心です
でも、子どもにとって本当に必要なのは、“答えを与えてくれる人”ではなく、“一緒に考えてくれる人”かもしれません
自分の経験は「教訓」として伝える
皆さん就職氷河期世代は、望んだ進路に進めなかった、あるいは仕事を選ぶ余地がなかった──そんな苦い経験をしてきました。だからこそ、「失敗してほしくない」という気持ちは誰よりも強いはずです
でも、当時の皆さんと今の子どもたちでは、社会も教育も選択肢も、まったく違います
だから過去の経験は「こうしなさい」ではなく、「私はこうだった」「こういう後悔がある」「こうしてよかった」という“材料”として伝えることが大切です
経験は押しつけるものではなく、分かち合うもの。
そうすることで、子どもは自分なりの考えを深めていけるのです

「大学・大企業=安定」という価値観を見直す
進路の話になると、「とりあえず大学」「できれば公務員」「とにかく正社員」といった“安定志向”が出てきがちです
けれど、先が読めない今の社会では、それが必ずしも正解とは限りません
それよりも、「どんな仕事がしたいのか」「どういう生き方がしたいのか」「何に価値を感じるのか」といった本人の意思を尊重しながら、一緒に選択肢を考える時間が、何よりの“キャリア教育”になります
安定を求める気持ちは否定せず、でも「その安定は誰が、どうやってつくるのか」を一緒に考えることが、これからの親の役割ではないでしょうか

答えではなく「考える力」を育てる
進路に“正解”がない時代だからこそ、私たちが子どもに渡せるものは「判断力」や「自分の軸を持つ力」です
✔ どんな情報を信じるか
✔ 迷ったとき、どう決断するか
✔ 失敗したとき、どう立て直すか
こうした力は、親の一言や態度がきっかけで育っていきます
「自分で選んでいい」「失敗しても大丈夫」「一緒に考えよう」──そんなメッセージを日々の中で少しずつ伝えていくことが、子どもにとっての支えになるはずです。
「進路を考える」とは、人生を考えること
子どもの進路とは、単に職業や学歴を決める話ではなく、「これから、どう生きるか」を考える機会です
それは、親にとっても同じです
自分がどんな時代を生き、どんな選択をして、何を大切にしてきたのか──
進路というテーマを通して、親子で人生を語り合える時間をつくることができれば、それ自体が何よりの“教育”になるのではないでしょうか

最後に
親世代は、決して“恵まれたスタート”を切ったとは言えないかもしれません
けれど、だからこそ、言葉にできること、寄り添える気持ち、伝えられる知恵があります
子どもがこれから生きていく社会は、変化も不安も多いけれど、そのぶんチャンスも広がっています
自分の人生を“選ぶ”勇気を持てるように──
親としてできることを、できる形で、少しずつ届けていきたいですね
大学に行くことだけが、進路の正解じゃありません。「何を学ぶか」「どう働きたいか」から考えると、『とりあえず』ではなく『本気で』学ぶ意味も見えてきて、専門学校のほうが合う人もたくさんいます。どんな分野があるのか見てからでも遅くありません。
あなたに合った専門学校がみつかるかもしれません。
| 専門学校は都道府県の認可校です |

関連記事
大学指定校推薦━うつ、退学、親の安心で子どもが苦しむことも
読者対象
最新情報
- 子供が大学を辞めることになる前に
- 「ありがとう」が聞こえる仕事へ。専門学校という選択
- 大学行きたくない 親に言えない
- 社会人から保育士になるには
- 「売り手市場」でも、やりたい仕事に就けるとは限らない!?
- 知らない人が結構多い!?専門学校AO入学エントリーに関する誤解
- 高校生の進路「早期内定」には要注意_複数校を比較して決めよう
- 「大学やめたい」「大学ついていけない」人がホントに多いんです
- 専門学校はメンタルとモチベ-ションを支える伴走型の環境です
- 大学受験につまずいても専門学校という選択肢、大学編入制度も
- 大学卒業後に専門学校を卒業した人_最終学歴は【大学卒】です
- 「進路 親のいいなり」―あなたの人生の”主役”は誰ですか?
- 大学中退から専門学校|卒業時は「新卒採用+スカウト型」就活
- 知らないと損 ハローワーク経由で “安く”保育士資格を取る制度
- 社会人から保育士に!専門学校で学ぶメリットと支援制度
- 内閣支持率「若者の価値観の変化」そこから見える進路のカタチ
- Fラン大・事実上無試験大の学生は企業からどう見られている?
- 経営悪化の私立大学に文科省が指導強化―価値のある進学とは?
- 親が進路を考えてくれない_どういう事?どうしたらいい?
- 専門学校は本当に楽しい?前向きの理由は在校生が感じる充実感
- 通信制専門学校_自分時間と両立し「資格・スキルを身につける」
- 大学の年内学力入試で進む、新たな「大学ミスマッチ」!?
- 行く価値のある専門学校とは?分野選びの指針と考え方
- 大学中退 親の気持ち
- 年内学力入試の導入で、「Fラン vs 専門学校」はもう古い考え方
- 年内学力入試が増えると、Fラン大学が見えにくくなる!?
- 専門学校に偏差値はある?知っておきたい入試の仕組み
- 大学年内入試拡大で専門学校の価値が上昇するこれだけの理由
- 「学びたい学生を迎えたい専門学校」と「人を集めたい大学」の違い
- AI時代に「とりあえず大学」「どこかに就職」の感覚じゃダメ
- ホテルで働きたい_方法はいくつかあります
- 社会人から専門学校へ_不安要素を解決!完全ガイド&学校紹介
- 大学を中退して専門学校へ_新たなスタートが生む自信と未来
- 大学中退後の3つの道:今すぐ中途採用・新卒正社員・公務員も
- 大学の年内学力入試が進む一方で──注目したい専門学校の実力
- AIで仕事はどうなる?高校生のための進路とキャリアガイド
- オールドメディアが報じない「専門学校」の実力こそ本当はスゴイ
- 大学中退 人生終了 今は辛い気持ちでも、必ず立ち直れます
- 子どもが大学を辞めたいと言ったら_専門学校で2年後正社員に
- リハビリの仕事に就くには:理学療法士と作業療法士の違いと、キャリアの選び方
- 「公務員になってほしい」保護者へ_各省庁に強い語学専門学校
- 理学療法と作業療法は何が違う?_やりたいリハビリはどっち?
- 大学中退は終わりじゃない。2年で「企業が欲しがる人材」になる
- ホテル専門学校に行く意味ある?―意味もあれば価値もあります
- ホテル専門学校って厳しい?ホテル業界はこんなに変化している
- 医療現場をテクノロジーで支える仕事— 臨床工学技士とは?
- 保育士を目指す大学と専門学校の違い、どっちがおすすめ?
- 映像クリエイターを目指す専門学校_きっと観てる“実写”映像
- AI時代のIT業界の目指し方_大学? 専門学校? 選び方完全ガイド
- 特色ある学科・学び方の専門学校
- 指定校推薦で大学中退した子どもへ – 親ができるサポートとは
- 「なんとなく大学」合わずに中退_仕事観で出会えた専門学校
- 高校生の子供が進路を迷っている、親はどう対応すればいい?
- 「就職ミスマッチ」は避けられる!? 専門学校=業界付属校の強み
- 大学中退から専門学校「再スタート迷子」にならない進路の選び方
- Fラン大と専門学校どっちがいい? そもそも「次元が違う」話
- 高校卒業してからじゃ遅いんです_就活迷子にならない進路選び
- 専門学校の就活は「スカウト型」_大学の就活は「売り込み型」
- 専門学校のいいところが今の高校生に合っている7つの理由
- 大学中退は親泣かせ?親の気持ち_心配は当然・次どうするの?
- 高校1・2年生の進路選び、親子でチェック指定校推薦の”注意点”
- Fラン中退する人、専門学校で伸びる人、子どもに合う進路とは?
- 指定校推薦の退学者が増加中_高校と大学の”取引”に生徒は不在
- Z世代の再起動=親世代に定着した「常識」の上書きが始まった
- 氷河期世代の子供(Z世代)の君へ 「自分らしい」進路の見つけ方
- 指定校推薦デメリット_大学進学前に親子で確認したいこと
- 専門学校へ行こうよ
- 未経験でもゴールが見える専門学校_行くメリット
- 「いい大学じゃないと、いい会社には入れない」は本当?実はね!
- 大学ミスマッチの先に見え隠れする就職ミスマッチ・退職代行
- 高校卒業後どうする?どうしたい?で、悩んでいるあなたへ
- Fラン大に進学したら「まわりが驚くほどやる気がない」は本当?
- 指定校推薦で、「うまくいった人」「失敗した人」に学ぶヒント
- 高校2年で進路が決まっていないけど、何か問題ありますか?
- 「専門学校意味ない」は間違い──そう言えるのは実力のある人
- 評価は学歴から学習歴へ_人材採用が“進化”「令和の真価論」
- 大学のオープンキャンパスで見た、親子のリアルなすれ違い
- 親に進路を反対されたらどうする?
- 学部が決められないのに大学進学?─進路の矛盾に気が付いた
- 学歴にこだわる親をどう説得する?親の理解と子供の進路戦略